
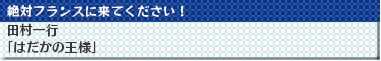

©池上直哉(Naoya Ikegami)
大駱駝艦なのに子供向け? しかもアンデルセンの物語? 想像がつかないけれど、なんだかワクワクする。このワクワクは期待を裏切らず、あうるすぽっとに入った途端にそこはもうはだかの王様の国。柱や壁にたくさんの絵が書いてあるし、ホールのある階には巨大なはだかの王様がデーンと構えている。作品が始まれば、これまでの舞踏のイメージをぶっ飛ばしてくれて、舞踏なのにガンガン踊って、背筋をぞくっとさせて、めちゃ楽し。動かない装置なのに、あっという間に場所が変わってお城の中だったり外だったり。確かにアンデルセンの「はだかの王様」だけれどジャポニズム感覚で、サクッとした皮肉や風刺も良い味加減。昼の回は子供が多いので、わいわいとあちこちで声が聞こえるそうだが、夜の回がそこまで盛り上がらないのは、日本人の慎ましさゆえ? フランスだったら子供に負けじと大人も爆笑するんだけどなあ。
これは絶対にフランスで上演してもらいたい。子供向けの舞踏作品なんてないし、台本は誰もが知るところなのでわかりやすい。明るい舞踏なのにおどろおどろしいところがあって、この違和感はフランス人の好むところ。待ってま〜す。(8月27日あうるすぽっと/あうるすぽっと+大駱駝艦プロデュース)

©池上直哉(Naoya Ikegami)
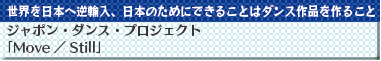

photos by Takashi Shikama
海外で活躍する5人のアーティスト(遠藤康行、小池ミモザ、柳本雅寛、青木尚哉、児玉北斗)によるジャポン・ダンス・プロジェクトが2年ぶりに行われた。日本にも素晴らしいダンサーも作品もあるけれど、言葉も習慣も違う中で経験を積んだ人たちがもたらすものが、良い刺激になってくれるはず。
今回はゲストとして、元フォーサイスカンパニーの島地保武とニューヨークから帰国したばかりの大宮大奨、国立バレエ団からは小野絢子、八幡顕光、米沢唯が加わった。島地はフォーサイス作品とは違った一面を見せ、海外組から刺激を受けたのであろう、国立バレエ団の3人も負けてはいない。繊細かつダイナミックでキレのある踊りを見せてくれた。
ダンサーの個性を生かしながら、普段着のような作品は見る側にとって入り込みやすい。メガネをかけて、何やら哲学的な資料をマイクの前でしゃべる児玉北斗。わかるようでわからない言葉の羅列が音楽に聞こえてきた頃、ドスンドスンと現れる木々。憩いの場所のようだけれどなんか異様。最後まで顔を見せない男(遠藤康行 )が皆を操っているようで、木を持ち上げるとその場が硬直し、床に下ろすと元の情景に戻る。そんな中で人々は、お祭り騒ぎのように踊り、自己主張し、こもり、悩む。気に入らない振付家のワークショップにはひとりずつフェードアウトしてしまう光景は、自分の経験とも重なって苦笑した。嘘なのか本当なのか、ダンサーのポートレイトを聞いていると、みんな苦労を物ともせずに頑張っているのだなあと感心する。まさにタイトルの「スティル/ムーブ」で、楽あれば苦あり、良い時も悪い時もあって、走ってみたり、止まりたくないのに止まらざるを得なかったりするときもあるけれど、それでもやっぱり人生は続いていくのだから、 今をしっかり生きようよ。そんな思いが伝わってくる。
ストーリーがないために全体のまとまりに欠ける印象があったけれど、語りあり、笑いありのバラエティに富んだ作風は、各場面から何かを感じればそれで良いのであって、日本にないものを伝えたいという主催者の意向は伝わったと思う。離れた場所に住むアーティストがひとつにまとまるのは容易なことではないけれど、こうして外からの風をもたらしてくれる企画を応援したい。
最後になったが、ヨーロッパで注目されている舞台美術家の針生康の装置が素晴らしく、シンプルなのに多くを語り、ダンサーと共に存在している感じがいい。(8月26日新国立劇場ゲネプロ所見)

photos by Takashi Shikama
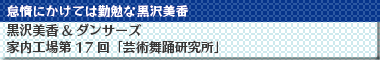
黒沢美香というと「怠惰にかけては勤勉な」というフレーズがすぐに頭に浮かぶ。最近になって気がついたのだが、これはまさしくフランス人のメンタリティで、フランス人も楽をするためには努力を惜しまない人種。黒沢美香には是非フランス人とコラボしてほしいと思う。
東京新聞主催の全国舞踊コンクールで何回も現代舞踊第2部で1位になった黒沢は、私にとっては神様のような存在で、いつも冷めた顔をしていたのを記憶している。もう少し大人になって当時通っていたダンススタジオに黒沢が顔を出して、その時に初めて笑顔を見た。そして、天上にいた人が自分の横にいて日常会話をしていることに感動を覚えたのを記憶している。その後何回か今のスタジオクロちゃんに行く機会があり、ここにはコンクールで1位を取れる仕掛けがあるのではないかとあちこち覗いたが、目立ったものは何もなく、そのスタジオを今回何十年ぶりかで訪れた。コンクールで入賞した盾が並び、厳しい指導のもと、汗と涙で濡れていない部分がなかったという床があり、窓から土手を歩く人が見えるのんびりした稽古場は昔とちっとも変わっていない。踊りのうまい黒沢美香は、ニューヨークでの在外研修員時代も日本にはない新しい感覚をどんどん吸収しつつガンガン踊っていた。それが帰国後に「黒沢美香は踊らない」という評判を聞くようになり、見に行った「船を眺める…」シリーズでは、噂通りほとんど踊らず動かず。熱帯夜が続いて寝不足だった私は、スタジオ200のクーラーの心地よさに爆睡し、目を覚ましても情景はほとんど変わらなかった記憶が残っている。何が彼女をここまで変えたのだろうかと不思議に思っていた。その時の共演者だった太田惠資との21年ぶりの共演を是非見たかったのだが、日程の関係で見ることはできなかったのは本当に残念だった。
さて、今回見た家内工場第17回目の 「芸術舞踊研究所」は、黒沢が踊ると思って期待して見に行ったのだが、あいにく踊らず、 秋山珠羽沙、大崎晃伸、高野真由美の3人へのワークショップ的作品だった。黒沢が簡単なフレーズを与えて踊らせ、アドバイスをして繰り返すこと延々。期待していたこととは違ったので少しがっかりしたのだが、見ているうちに面白くなってきた。黒沢の指示を三人三様に理解するから、動きが似ているようで異なるし、ちょっとしたアドバイスで踊りが変わっていく。振りを正確にコピーするのではなく、最低限のところが合っていればそれでよく、そのあとを自由にさせることで、動きに個性が出てくるのだ。分かりきっているはずのことだけれど、こうして客観的に見るとなかなか面白い。それにそこには黒沢美香のセンスがあり、これが好きで昔から見ていたのだと改めて思った。
そして何より、彼女の人生はダンスそのものなのだと感慨深く思った。(8月27日スタジオクロちゃん)

©砂山典子
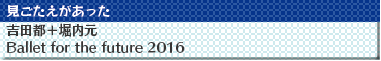
堀内元監督の下に特別ゲストの吉田都に加えて、国内外からのゲスト参加によるバレエ・フォー・ザ・フューチャーが行われた。昨年の成功により今年はさらに会場を大きくして東京文化会館での公演となった。
「Vivaldi Double Cello Concerto」(堀内元振付)に始まり、「Bloom」(ブライアン・イーノス振付)「チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ」(ジョージ・バランシン振付)「More Morra」(堀内元振付)「Romantique」(堀内元振付)という構成で、バラエティーに富んだ組み合わせには起伏があり、最後まで楽しんで見た。
幕開きの「Vivaldi Double Cello Concerto」は、赤や紫のアクセントのついたチュチュの女性と、白い衣装の男性による軽快な踊りがテンポの良い構成で綴られるオープニングにふさわしい作品で、ヴィヴァルディの起伏のある曲を綿密に分析したムーブメントに、堀内が率いるセントルイスバレエ団の雰囲気を感じた。続く「Bloom」は、一転してコンテンポラリー的な作風で、男女の揺れ動く心境が印象に残った。「チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ」は、パリ・オペラ座版、NYCB版を見ていたので、日本人ダンサーがどこまで表現できるかに注目したが、日本人ならではの繊細な踊りは欧米のものとは一味違い、新鮮だった。「More Morra」は、黒い衣装の男女が入れ替わり立ち替わり相手を変え、デュエットから群舞までリズミカルに変化する構成に見入ったが、軍隊行進や爆撃を連想させる音とフラッシュは、テロやシリアでの戦争が身近な私にとっては辛いものだった。
この中で特に印象深かったのは「Romantique」。吉田都が踊ったこともあるが、儚い夢の中での幻想のシーンに出でくる吉田は軽やかで、空気と戯れるようだった。そして堀内元の、揺るぎないテクニック、高いジャンプ、キレのある踊りは年齢を感じさせず、全く素晴らしい。また、ワシントン・バレエのソリスト木村綾乃のしっかりした踊りが印象に残った。(8月31日東京文化会館)

©Hidemi Seto
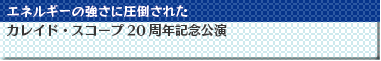

©塚田洋一
まだ高校生だった二見一幸を見て、踊りの上手い子だなあと思った記憶が残っている。そして何十年ぶりかで見た二見は期待を裏切らず、相変わらずいい踊りをしていた。田安知里はもちろんのことだが、出演していたダンサーのレベルも高い上に、男性ダンサーが9人も出演しているのは圧巻。また、ダンサーひとりひとりがきっちりと踊りこなして作品がきれいに仕上がっていて気持ちよかった。作品の仕上げは重要なことで、これが後味の良さの有無を決める。また、作品は作れば良いというものではなく、当日の舞台空間をどう埋めるかということと、ダンサーがどこまで作品を理解して入り込んでいるかにもよるからだ。これだけの人数のダンサーをまとめることはそう簡単なことではないと思う。
今回はカンパニー設立20周年記念ということで、3作品の再演と新作の上演となった。流れるようなムーブメントは、軌跡の余韻を目に焼き付け、ダイナミックに風が巻き起こる。構成も綿密に計算されているので空間に隙がない。フランス留学時にたっぷりフレンチテイストを吸い込んだのか、どこか日本離れした作風だと思ったのは、私のフランスびいきによるものかも。ただ、終わってみるとこれといった強い印象が残らない。ひとつひとつの作品は良くできているのに、全体を通して見るとヤマがないのは、作品の傾向が似ているからか、使用曲が似ているからか。美味しいものばかりを食べているうちに新鮮味がなくなる感覚だったのが惜しい。
とはいえ、これだけレベルの高い作品に出会えたのは収穫で、今後のさらなる活躍を期待したい。(9月3日全労災ホール・スペース・ゼロ提携公演)

©塚田洋一

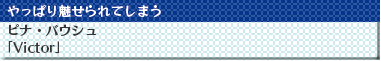
まず、ピナの公演を見る場合の絶対条件は、なるべく舞台に近いオーケストラ席をゲットすることだと思う。そうしないと本当に楽しめない。なぜなら、ダンサーが客席に降りてきたり、話しかけたりするからだ。特に古い作品は要注意。テアトル・ド・ラ・ヴィルと違って、シャトレ劇場はイタリア式劇場だから2階席以上だと見えない部分もあるので面白みが半減してしまう。高くても良い席で見ることは必須なのだと実感した。
さて、幕が開けば天井近くまで守られた土に圧倒される。その上に椅子があり、男がひとり、シャベルで土を下に落としている(これは5階席では見えない)。このそびえ立つ土の壁に囲まれた場所に、スタンドピアノが1台。腕のない真っ赤なドレスを着た女性がにこやかに出てきて客を見ている。男が毛皮のコートを羽織らせて、優しそうだが有無を言わさずに女を連れ去ろうとし、女はとても未練がましく、少し泣き顔になりながら静かに退場する。その表情が何を語るのかは、もう少し後にわかる。絨毯に巻かれてしまう女、死んだカップルに結婚の儀式を行う男。手をいじりながら歌い続ける女を寝かせ、着ていたコートをかぶせて殺す男。土の壁の上から土を落とす男、ここは墓穴の世界なのかもしれない。生と死、ナンセンスな寸劇に見えるけれど、社会への皮肉や風刺が隠されている。もちろん遊びもあるけれど。キラキラ輝くドレスとつばの広い帽子をかぶったブルジョア風の女性の腕にはバケツ。犬のフンを集めるためだ。連れの男は、トレンチコートに裸足で靴もズボンも履いていない。オークション会場では、生きた犬まで競売にかけられる。その横ではヤギを差し出し物々交換。やる気のないウエイトレス3人のカフェに入っても、注文の品は出てこない。一流レストランのウエイターは厳かに木を切り、毛皮の女は椅子に座り直した瞬間に丸裸の尻を見せる。ステーキ肉はトウパットになり(これは映画にも出てきたシーン)、石を持った女は叫び続ける。パンにジャムとバターを塗ったものが配られ、ポストカード売りのお兄さんが客席を回る。次から次へと起こる予期しない出来事に興奮するも、上から土が落とされる瞬間に過ぎるなんとも言えない冷めた空気に我に帰る感じだ。
ありそうでなさそうな風景。ブルジョアと平民、金持ちと貧乏人、老いと若き者、男と女、生きる者と死んだ者。その対極が皮肉を込めて描かれている。土が落とされる中、全員が長座になって髪を垂らしたラストは、ゾンビのようだった。さらりと笑いを込めてのメッセージ。笑っているようで、実は恐ろしい現実があることに気づく。見るたびに新たなことを発見するのは、ピナの思慮深い構成と、ダンサーの演技にもよると思う。ブッパダール舞踊団のダンサー達は、ダンサーである以上に女優でなくてはならない。実際にありそうでないことをいかにリアルに演じるか、それによって観客がその感情に同調することによって、作品の面白さが見えてくるからだ。初演時のダンサーはほとんどいないけれど、新しいダンサーがそれまでとは違ったものをもたらし、それをまとめる人によって作品は生き続け、成長し続ける。(9月10日Théâtre de Chatelet/Théâtre de la Ville提携公演)

©Jochen Viehoff
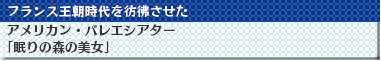

©Ula Blocksage / Opera national de Paris
パリ・オペラ座新シーズンは、招待カンパニーのABTによる「眠りの森の美女」で始まった。アメリカのバレエ団によるロシアのラトマンスキー新演出による作品は、ヌレエフ版を見慣れた目には退屈に感じただろう。テクニシャンとして有名なジリアン・マーフィーは、ただひたすら清楚で控えめなオーロラ姫を踊り、オーロラ姫を目覚めさせたデジレ王子は真っ赤な服と黒い帽子の貴族で、ゆらゆらとしたデュエットでふたりの愛を語るからだ。しかし、これにはカラクリがある。ラトマンスキーは、220ページにわたるステパノフのノーテーション(舞踊譜)を元に、原盤の復元にとどまらず、これを現代のダンサーが踊るとどうなるかということも考慮しながら再構築したという。これを考えれば、歴史的改革とも言える作品だ。確かに優雅で気品があり、綺麗な絵本を読むような、物語そのものの優しさを表していた。
幕が開けば、フランス王朝風の装置。衣装もチュチュではなく、膝丈までのふわりとしたスカートに身を包んだダンサーたちで、シーンごとにパステル調の色合いが変わり、アクセントに数人だけが濃い色の衣装を着けることで全体が締まっている。
オーロラ姫のジリアン・マーフィーは愛らしく、安定したバランスでひとつひとつのパを丁寧にこなし、ダンスそのものが演技にもなっている。リラの精を踊ったステラ・アブレナはプロローグと1幕では表情が乏しく見えたが、2幕以降は役に見合う表情と演技で存在感を現した。高貴な雰囲気をかき回すカタラビュート役のアレクセイ・アグディンでの演技が際立って面白く、特に誕生パーティーの準備での慌てぶりは真に迫っていた。また、カラボスを踊ったクレイグ・サルステインの不気味さは会場全体を飲み込むような迫力。デジレ王子(コリー・スティームス)とオーロラ姫のデュエットは、見慣れたヌレエフ版よりずっと地味に見えたが、気品のある優雅な踊りはまさにおとぎの国にいるようだった。結婚式の場面で青い鳥を踊ったZhiyao Zhangはスラリとした容姿で、まさに鳥のように軽やかなジャンプを披露し、大きな拍手をもらっていた。子役は全てパリ・オペラ座学校の生徒で、よく演技して踊っていた。
高度なテクニックを見ることに慣れてしまった目には、物足りなかったかもしれないが、19世紀にプティパが描いた世界を現代に通じる表現方法で再構築したラトマンスキーの地道な努力が見事に実った公演となった。(9月9日L’Opéra Bastille)

©Ula Blocksage / Opera national de Paris

©Ula Blocksage / Opera national de Paris
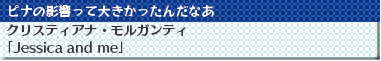
ピナの元で長年踊っていたダンサー、クリスティアナ・モルガンティが自身を語る「ジェシカと私」。個性的で好きなダンサーのひとりだったから、ピナ亡き後もこうしてソロ活動をしてくれることを嬉しく思う。作品はピナの影を感じるもので、ピナとの20年は、彼女の人生そのものだったようだ。
イタリア人だけれど、フランス語も話す。「日本語でも演じられるのよ。日本語はね、イタリア語と発音方法が同じなの。」ピナは上演国の言葉で演じることをモットーにしていたからね。「私は今ここで泣くことも笑うことでできるの。」ピナの作品に出ると言うことは、ダンサーであると同時に女優でなくてはならないから。自分を語り、踊る彼女にテープレコーダーからの質問が浴びさせられる。「ピナがいなくなってこれからどうするの?」こんな質問を今まで何度も受けてきたのだろう。もう勘弁してというふうにスイッチを切り、その場を離れた。
イタリアでバレエを習っていた子供の頃、才能はありそうだけれど胸が大きすぎると言われて凹んだ思い出。1987年にドイツに渡ったけれど、ちっとも寂しくなかったと言う。そしてピナと共に20年。白いロングチュチュが燃えているかのような映像は、情熱の炎とも、過去を全て燃やしてしまいたい気持ちとも取れた。そこに現れた小さなクリスティアナ。それはピナとの思い出でもあり、これからもアーティストとして活動してく未来の姿でもある。「クリスティーナじゃなくて、クリスティアナ!」カセットコーダーに向かって叫ぶ姿は、名前を間違えられ続けてきたからだろうか。「ピナはね、私のタバコの吸い方が下手だとずーっと言ってたわ。そして言うの、タバコを右側から吸って、ゆっくり顔を左側に向けて、フーッと吐くの」。やっとピナの思い通りにタバコを吸う仕草ができた頃、ピナはいなくなってしまった。(9月29日La Comédie de Clermont)

©Claudia Kempf

カロリン・カールソンの創作意欲は衰えることを知らず、毎作品ごとに新しいメッセージが送られてくる。過去の作品でも時の経過を感じさせず、新鮮な気持ちで見ることができるのにはいつも感心する。作品が綿密で思考が深く、身近なテーマをユニバーサルに語っているからだと思う。
精力的な活動を続けるカロリン・カールソンの「ナウ」(2014年)では、フランスの哲学者ガストン・バシュラールの「空間の詩学」やルドルフ・シュタイナーの思想に触発され、例えばダンスというのは瞬間芸術で、次の動きに移った時、その前の動きはもうここには存在しないこと、同様に昨日も明日もなく、今日、今しか存在しないことを表したかったという。だからタイトルは「今」。
「『今』と言っても、この『いま』は1分後には過去になってしまっているわけで…」というユハ・マルサロの語りは、マキシム・ルイズとブノワ・シモンの実物と見間違うバーチャルな美術と重なって、時空を超えた世界を表す。雪に埋もれた家、誰もいない家の中をランプを灯して廻る人。街には様々な人が行き交い、カフェのテーブルに座って話していることは次々と過去に流れ、季節も人も流れる。そんな中で生きる私たちの、今、ここでしか感じられないエネルギー。メランコリーにならずにテンポの良い動きに見入ったと同時に、カールソンの詩的な哲学の世界に引き込まれた。(9月30日Théâtre National de Chaillot)

©Patrick Berger
|

