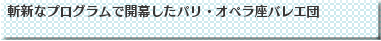

オペラ座ガルニエ宮グラン・フォワイエ
今シーズンのバレエの開幕は招待カンパニーのアメリカン・バレエシアターだったが、パリ・オペラ座バレエ団は4人の前衛的振付家のソワレで始まった。イギリス生まれでベルリン在住のアーティスト、ティノ・セーガルは開場時に4作品をガルニエ宮のホールや廊下で繰り広げ、舞台ではジャスティン・ペックの「In creases」とウイリアム・フォーサイスが今年7月にパリ・オペラ座バレエ団のために振り付けた「Blake Works 1」の再演、そしてクリスタル・パイトがパリ・オペラ座に振りつけた新作「The seasons’ canon」と続き、一夜を締めくくる形でティノ・セーガルのこれまた驚きの新作「(Sans titre) (2016)」と、ミルピエ前芸術監督の想いが詰まった演目だった。
「午後7時半開演ですが、ティノ・セーガルの作品は開演1時間前から始まります」との案内。入り口の荷物検査に時間がかかるからと6時過ぎに行ったら、鉄の扉は固く閉じたまま。荷物検査の係員に文句を言っても。知らぬ存ぜぬ、上からの指示がなければ開けられない、6時半から公演が始まるとは聞いていないと埒があかない。それが6時半きっかりに門が開いてガルニエ宮のホールに入った途端に驚いた。「This is so contemporary」と叫びながら係員の制服を着たダンサー達が踊りまくっている。客を迎え入れるようにじっとしていたかと思うと、いきなりスキップしながら「ソー・コンテンポラリー」だもの。驚くやら吹き出すやら。廊下やホールでのパフォーマンスは昨年のボリス・シャルマッツの「20世紀のための20人のダンサー」と同じ形式で、過去の4作品をホールや廊下で演じているが、動きが地味で、オブジェと見間違うこともあったけれど、歌い、踊りのパフォーマンス。ラップのような歌を歌いながら数人で動いているのは見つけやすいが、廊下やホールの隅の方でうずくまっていたりすると、気づかずに通り過ぎる客もいて、建物やオブジェの一部になりながら動いているダンサーの、物と人間の境目で演じているのが面白く、目が離せなかった。

オペラ座ガルニエ宮の廊下
座席に着くまでの奇妙な散歩の後は、ジャスティン・ペックの「 イン・クリーシズ」で幕を開けた。2台のグランドピアノが舞台後方に置かれ、フィリップ・グラスのミニマルながら流れる曲に乗ってのネオクラシック作品は、初演時よりも踊り込んでやわらかくなったように思う。オニール・八菜がメインで踊り、キレとしなやかさのある踊りに魅了された。芯の太い踊りをするヴァランティーヌ・コラサント、さらに落ち着きを増したマーク・モロー、シャープな踊りに定評のあるヴァンサン・シャイエ、柔らかさを増したイダ・ヴィキンコスキ、オーバーヌ・フィルベールも良い踊りをしていたが、ヴィキンコスキと組むと背の小ささがマイナスに映ってしまったのが残念。ダニエル・ストークスとアレクサンドル・ガスもよく踊りこなしていて、若手の活躍が著しい幕あきにふさわしい作品だった。

「In creases」 Opéra national de Paris©Julien Benhamou
昨シーズン最後の演目として発表されたフォーサイスの新作「ブレイク・ワークス1」の再演は、出演者を前回とほとんど変えずに踊り込んだようで、素晴らしい仕上がりになっていた。席によって印象は変わるもので、少し遠くの席から見ると全体の流れが見えて面白く、綿密な構成はバレエ・フランクフルト時代と変わらないという印象を持った。軽そうに見えるけれど、スピードがあり、フォーサイスならではの動きがあちこちに散りばめられていて、バレエ・フランクフルト時代のファンとしては嬉しい。
メインで踊ったリュドミラ・パリエロが群を抜いて素晴らしく、目が離せない。全く解放されていて、バランスを楽しみ、伸びを楽しみ、音楽が体から溢れている。これぞフォーサイス節。
フランソワ・アリュとレオノール・ボーラックのデュエットは、以前にあったスピード感が薄れた代わりに考えの違うふたりだけれど、支え合い、意見をぶつけ合いながら成長しているカップルの対話が見えた。
ユーゴ・マルシャンのダイナミックでしなやかな踊り、そして、コリフェのポール・マルクがバレエ・フランクフルトの再来かと思わせるようなダイナミックな踊りをしていたのが強く印象に残った。
リュドミラ・パリエロとジェルマン・ルーヴェの静かな踊りで終わるのがあっけないような気もするけれど、ほわっとしたラストは走馬灯のようにそれまでの場面を思い起こさせる効果がある。イン・ザ・ミドルからブレイク・ワークス1へ。時代は違ってもやっぱりフォーサイスの作品は魅力的だ。

「Blake Works 1」 Opéra national de Paris©Julien Benhamou
クリスタル・パイトは、新作「ザ・シーズンズ・カノン」で衝撃的なパリデビューを果たしたといえよう。
オーロラのような、いや、宇宙的な光の柱が形を変え光を放ちながらゆっくりと下手に移動すると、その下に人の塊が見えてきた。その塊が細かく揺れ、次第に大きな波になり、湧き上がる生命の力に大地が耐えきれないようにぐわっと動いた。舞台に湧き上がる人の波。その大きな流れの中に、ポツンと投げ込まれた石、あるいは水の流れを妨げる岩が現れたかのような流れは別の波を作り、塊が長くなり、それが砕けて散り散りになっては吹き寄せられたように集まる。マックス・リヒターのヴィヴァルディー「四季」のリメイク版がこれに煽りをかける。オペラ座のダンサー54人が固まり、蠢き、舞台に広がる大群舞だ。エトワールもプルミエダンサーもスジェもコリフェも全員がひとつになってものすごいパワーを発している。それはまさに生命そのものの躍動で、春夏秋それぞれの季節の中で生きる歓びと強さが伝わってくる。深々と雪が降る冬には、どっしりとしたエネルギーが静かに流れ、やがて来る春に向けて飛び出す時期を待っているかのようだった。どのシーンも力強いけれど、トーンは変わり、季節が見える。大地と、それを構成する5つの要素、そこに流れる季節、その中で暮らす生命が描かれた壮大な作品で、形の面白さとそこに生まれるエネルギーの祭典、まさに大地のカノンだった。

「The seasons’ canon」 Opéra national de Paris©Julien Benhamou
「ザ・シーズンズ・カノン」の興奮も冷めやらぬ会場に、別の驚きが走った。いきなりエレクトリックな音楽が流れ、リズムに合わせて会場の照明がチカチカしはじめた。何これ? 会場は一瞬唖然。天井画の周りのライトがチカチカ、緞帳が降りたり上ったり、袖の内側まで見えるし、黒幕が5本も降りたり上ったり。会場全体が踊っている感じだ。ガルニエ宮がディスコに変身したか?! 一番後ろの幕が上がれば、ガラでしか見られないシャンデリアの間が開いた! なんと美しい。その光の中からダンサーひとりが後ろ向きのままパドブレで客席に向かっている。袖からも男女がパドブレで舞台を横切り、3人がオケピットに落ちると。客席からあーという声が。なんとダンサーたちが客席のあちこちにいて踊り歌う。通路、ロッジの中、天井桟敷の席にまでいる! 終わればホールで歌を歌い、外まで案内してくれる。こんなオペラ座を見たことない! やってくれたな、ティノ・セーガル。タイトルは「(無題) (2016)」。
まさに超コンテンポラリーダンスの一夜で、オペラ座の改革を目指したミルピエの策略は見事に実った。そのミルピエはもういないけれど、素敵な贈り物にオペラ座ファンも満足したことだろう。好き嫌いはあるけれど、今の時代に合ったオペラ座であることも必要なこと。オペラ座バレエ団はコンテンポラリーダンスが踊れる最高のカンパニーだと言ったミルピエの言葉はここに証明された。(10月3日オペラ座・ガルニエ宮)

ミッシェル・ノワレの踊りを見ていて、手作りの踊りをする人だなあと思った。変な言い方だが、ノワレの身体に染み込んだムーブメントをつなげて表現している。ものすごく踊るわけではないけれど、日常の小さな動きを交えながらダンスというムーブメントを昇華している。ここ数年、ヒップホップやサーカスのアクロバットを取り入れた動きが流行っていて、それはそれでテクニック的に面白いし見栄えがするけれど、コンテンポラリーダンス特有のムーブメントも忘れてはならない。ノワレのこの作品のように、抽象的なムーブメントで見せていく作品は、深いところまで追求しないと途中で飽きてしまう。昨年創作過程としての一部をアヴィニヨン・オフで見たが、その時とは比べ物にならないほど踊りこまれていた。
まず、先にも述べたが、ノワレの体から出る動きが自然で心地よく、暖かいものを感じる。ブツ切れでとりとめのない独り言の合間に、客の膝に手を置いたり話しかけたりしても、嫌味がない。知り合いが寄ってきて話しかけてきたような親近感を感じて、思わず答えようかという衝動に駆られた瞬間にノワレはふっと遠くに行ってしまう。エフェメールのようなノワレの存在は、幻想なのか現実なのか、空間自体さえも不安定にさせてしまう。そこにダヴィド・ドルオーが現れてデュエットになるが、男女というよりふたつの細胞がくっついたり離れたりしながら、「ちょっと寄っかかってもいい?」「う〜ん…だめ」「じゃこれは?」「フェイントね」なんて会話が聞こえてくるよう。そして男が去ればまたいつもの日常に戻る。人生いろいろあって、悩んだり、はしゃいだり。こうして思い出や出来事は新しいものに重なって塗り替えられながら続いていくのだ。2004年のソロをこうしてデュエットに置き換えて、まさにパリンプセスト。うまいなあ。(10月6日シャイヨー国立劇場)

「Palimpseste Duo」©Sergine Laloux


「one mysterious Thing, said e.e.cummings*」©Jorge Goncalves
ヴェラ・マンテロとクローディア・トリオッジと言ったら、何が飛び出すかわからないアバンギャルドの女王みたいなアーティスト。そのふたりのソワレと聞いて、パリ北部のパンタンにあるCNDに行ってびっくり。いつものグレーの重い扉は消え去り、手前の図書館横のガラス張りの回転ドアが入り口になっていた。中に入ればホールには植木が置かれ、明るいイメージになっていた。有名な建築家の建物を勝手に改造したことに不満を述べる声もあるようだが、解放された空間は気持ちがいい。余談だが、現在のディレクションを不満に思う従業員のストで、初日の公演はキャンセルとなった。
さて、今夜はまずヴェラ・マンテロの3つの小品から始まった。1996年の「one mysterious Thing, said e.e.cummings*」は、見えるか見えないかの明かりの中から声だけが聞こえてくる。それが途切れ途切れで聞き取りにくいけれど、幾つかの言葉が繰り返されていることはわかる。次第に明かりが入って、目の周りにラメを入れた派手な化粧をして、ストッキングのような生地の黒の全身タイツを着て、おぼつかない足取りで言葉を発しながら、妙なジェスチャーをしているのが見えてきた。指を立てたり、胸の前で形を作ったり。言葉を音としても捉えているので、歌のようにも聞こえる時がある。ただこれだけなのだが、足が鹿の足のように二股に分かれた木の靴を履いていることにカーテンコールで気がついた。
「Perhaps she coule dance first and think afterwards」(1991年)は、四隅に置かれたアルコールランプの上に吊るされた子供用の黄色い長靴がゆっくりと溶ける中で行われる。緑のワンピースを着たマンテロは、テンポよく踊るのだけれど、顔をしかめてみたり、背中を丸めて首を引っ込めてみたりの奇妙なダンス。そのうちに心地よいジャズミュージックが流れてきたのだが、なんと、このへんちくりんなダンスが妙に音楽に合っていて、面白い。好き勝手に踊っているのではなく、ちゃんと音を分析して奇怪度を高めている。ちなみにマンテロはクラシックバレエを習い、 最初の作品をグルベンキアンバレエ団に振り付けたという経歴を持っている。
マンテロのヘンテコだけれど踊りのうまさに感心しながら待っていると、ごとごとと大きなものを動かす音が聞こえて来た。見れば、裸の体に白いテープを巻いて本を読みながら、ひどく前傾姿勢で進もうとしている。なんと、ベッドを引っ張っていたのだった。やっとの事で所定の位置につけば、ふわりと羽毛のごとくベッドに横たわる。真っ白いふかふかのベッドに横たわる姿は、高級娼婦のようで優雅。ところが枕の位置が悪いのか、体の置き場所が悪いのか、心地よさを求めて頻繁にポーズを変えている。でもどんな風に横たわってもダメ。首がはみ出ていたり、体がベッドに沿わなかったりして、うつ伏せになったり仰向けになたり横向きになったり、落ち着かない。本でも読んでくれるのかと思ったら、落ち着きのないまま終わってしまった。マネの「オランピア」のパロディだ。パロディというより、もしマンテロが娼婦だったら、こんな感じなのだろうか。見ている方が楽しい娼婦というのがいてもいいかも。もちろんこの作品のタイトルは「オランピア」(1993年)。
マンテロが今回古い作品を再演したのは、「ダンスは本のように保管できるものではないから、時々引っ張り出して見直すことで、また新たなものが見えて来る」からと。納得。

「Perhaps she coule dance first and think afterwards」 ©Jose Fabiao

「オランピア」©Jorge Goncalves
さて、クローディア・トリオッジの「Park de 1998 à aujourd’hui」は、3つのスタジを移動する作品で、突拍子のないオブジェとのコラボだった。ダンシングクイーンの曲が陽気な雰囲気を出す中、くわえタバコで小さなフィギュアにつけたスポンジを水に浸し、カンカンに熱した電気コンロに水滴を落としてジュッ。ボワっと水蒸気が上がり、頭の上の機械からはソーセージの輪が顔の前にバンバンと落ちて来る。顔が見えなくなろうが御構いなしに水をジュッとたらし続けていると、けたたましいベルの音が響き、ワンワンワンと激しい犬の叫び声を発する。別のテーブルへ移動して、金属のオブジェを机に引っ掻いて耳障りな音を出す。スタジオを移動して、緑のカーペットにプラスティックの木が生えた絨毯の上で、足を上げてタバコを吸って日光浴。せわしなくポーズを変えた後は、別の机に座って、またタバコ。ケーキのようなゼリーにナイフを刺して、その中からバドミントンの羽やガラクタをつまみ出しては、床の石鹸水が入った洗面器にぽしゃんと落とす。最後にようやく見つけた結婚フィギュアに満足してハッピーマリアージュ! 別のテーブルでは、アイスクリーム皿にアイスを乗せてベルトコンベアーに乗せるが、机の端で皿が床にどんどん落ちるのにもお構いなくアイスを乗せ続けるバカバカしさ。また別のスタジオへ移動してビデオ。ここでようやく種が明かされる。1982年に閉鎖したパンタン(CNDがある街)のタバコ工場で働いていた女性へのインタビューで、写真を見せながら当時の様子を語る。だから最初から最後までタバコを吸い続けていたのだった。昔はそこに大勢の人がいて生活があった。時代は流れ、最新だった機械は使い物にならない粗大ゴミとなり、がらんとした工場の中をたった1箱のタバコが、ガタガタとベルトコンベアーで運ばれていく映像が虚しい。最初に鳴ったけたたましいベルの音は工場のものだったのかも。トリオッジは自分とタバコ工場の歴史を重ねてリニューアルしたのだ。
1998年に初演した「パーク」はトリオッジの初期の作品で、これを今再演することで、 当時は感じられなかったものが見えてくるという。ヴェラ・マンテロ同様、古いものを今に合わせて再現することで見える新しさ。作品は演じる人の意思があればしっかり成長するものなのだとつくづく。
それにしてもバスケットボールのゴールって結構大きかったんだなあ。トリオッジはするりとその中に体を突っ込んで気持ち良さそうに回っている。奇妙なアーティストだけれど、本人も何かが崩れた奇妙な時間の中にいる感じがするそうで、変だと思っているのは見る側だけでなく本人もだというところに、妙な現実感を覚えた。(12月5日CNDパンタン)

「Park de 1998 à aujourd’hui」 ©Olivier Charlot
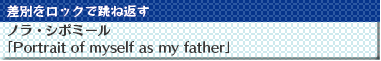
今年のテアトル・ド・ラ・ヴィルのシーズン初めは、アメリカのアーティストが続いている。そんな中でニューヨークのダンスのロックスターと言われるノラ・シポミール(Nora Chipaumire)の「Portrait of myself as my father」を見た。
ポップな曲が流れる中で「イッツ・ミー」と叫ぶシルエット。ノイズ音が響く中、マイクを持って走り、大声で叫んでいる。アメリカでは黒人だというだけでこんなに差別を受けるものなのだろうか。後ろにいた男は猿かゴリラの真似をしている。アフリカ人は人間とはみなされないことへの皮肉だろう。差別を受けた屈辱が塊となってエネルギーを発しているようにも見えるが、だからと言って始終怒っているわけではない。ラップを歌い、舞台を走り、3カ国語でまくし立て、ものすごい迫力だが、写真や前評判で聞くほど暴力的ではなく、パンチの効いたポエムという印象を残した。反抗と怒りが充満しているのだけれど、そこに優しさが見えるのは、ノラの性格ゆえだろう。舞台を仕切るノラのセリフを誇張するように踊る男と、アシスタントのごとくスポトを動かしながら照明を変えていく男。彼は客席の通路でも踊るというか爬虫類のような動きをして客を驚かせる。
同じ人間なのになぜ差別が生まれるのだろう。アフリカで生まれたというだけで受ける苦しみ。ノラが言うように、人は死ぬために生まれてきたのだろうか。それはちょっと悲しすぎ。(10月1日アベス劇場)

「Portrait of myself as my father」 ©Elise Fitte Duval

久々に訪れたジンガロ劇場。屋根付きの通路のような入り口を入った途端にジンガロワールドに引き込まれた。馬のオブジェの向こうには大きな馬小屋が見える。今日のスターたちがいる場所だ。その手前の待合室兼カフェレストランは、過去の作品の衣装や小道具が天井まで飾ってあるサーカス小屋で、入り口にはアコーディオンを弾くおじさんがいて、話しかけてくる。赤い幕が開けば、音楽隊の陽気な演奏が始まり、その後ろのドアが開くと彼らはすぅっと天高く舞い上がっていった。この音楽隊に先導されて馬小屋を通って会場へ。
薄暗い円形のステージにそろそろと馬たちが集まってきた。そこへスルスルと天使たちが降りてきて馬にまたがり、さあ、旅の始まりだ。
疾走する馬の上でのアクロバットはいつ見てもその迫力に驚かされる。その勢いとは対照的なバルタバス。少しくたびれたが酔っ払ったおじさんみたいにおぼつかない手さばきで馬を操り、ゆっくりと馬から降りる。哀愁を帯びた歌声に支えられるように彷徨う姿をかき消す音楽隊。チンドン屋フランス版という感じで、ラッパと太鼓で囃したて、ソーゼージ売りの声が響く。
馬の演技に目をみはり、アイディアいっぱいに次々と展開するシーンに体を乗り出し、喜怒哀楽に満ちた作品は2時間という長さを感じさせない。ここにはたくさんの天使たちがいる。下界の人生には限りがあるけれど、雲の上では永遠に続くスペクタクルが繰り広げられているのかも。
音楽隊の中にアジア系の顔を見つけてプログラムを見れば、Yuka OKAZAKIの名前。素敵なソロ演奏もあって、頑張って〜心の中で声援を送った。
大衆的になったという声もあるけれど、夢を与えてくれる作品は心が温まる。年末まで公演しているので、1年の締めくくりに良い思い出ができること間違いなし。(10月2日Théâtre Équestre Zingaro)

「On achève bien les anges - Élégies」 ©Hugo Marty
|

