
今年もランコントルの時期になりました。見たときは「?!」と思うのに、数年後には「注目の新人」として取り上げられる振付家が多いのが特徴のフェスティバル。今年は5月12日から6月17日まで29人の振付家を招待して行われた。日本からは南阿豆と三東瑠璃が選ばれたが、あいにく会期の前半しか見られなかったのでパス。では見た順番に。

紗幕が張られた白い床の四角いスペース。四隅から出てきた4人の女性が、服を脱いで部屋に入る。白い紗幕の後ろでぼんやりと見える皮膚の肌色が鈍く光り、ひとつの作業を繰り返すような動きのせいか、人間そっくりのアンドロイドが踊っているように見える。白い部屋からはみ出し、紗幕の前に立った4人のシルエットが黒く浮き上がり、一瞬だけ強い光が彼女たちの顔を照らす。その一瞬に彼女たちの素顔が見えた。
再び白い部屋に戻ると、さらに4人が四隅から出てきて、全員で輪を作る。すると、様相が一変する。スクリーンに万華鏡が浮き上がった。それは、彼女たちの動きを上からとらえたカメラが映し出したもの。輪がぐるぐると回り、花が開くように広がったかと思うとつぼみ、様々な形を作り出していく。
少しずつ部屋が明るくなると、スクリーンの動きと舞台の動きが重なり、不思議な模様を見せ始める。理屈ではわかっていても、このようなだまし絵は美しすぎる。(5月12日モントルイユNouveau Théâtre de Montreuil)

©Annavan Kooij
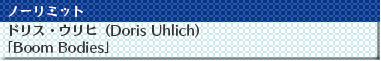
ブンブンという低く激しいリズムの中、舞台の前面に客に背を向けて立っていたダンサーたちは、床に広げられていた緑色の太い紐を体にくくりつけた。それはゴムでできているので、お互いに引っ張りあったり、引き戻されたりしているうちに、今度は縄跳びのように床に叩きつけ始めた。あっさりとやめると、ゴムを片付けて、座りポーズを取った。揺れたり、行き来したりのシンプルな動きを方向を変え、動きを変えて繰り返している。ひとりが新しい動きを始めると、ほかがそれに倣い、全員が同じ動きを始める。動きに個性が見えて面白い。似ていて異なるから。その動きをどのように消化しているかの違いが見える。これも個性。ただ、これが延々と続くと、こちらも飽きる。しかも音楽はブンブンの大音響が続いている。そこから何かが生まれることを感じるより、ダンサーの体力に感心した。シェークしたり、クラブで頭を激しく降りながら全てを忘れるように踊りに没頭する姿に見えたりと、 休むことなく激しく動き続けていることは驚異的でもあった。ブンブンと言う単調なリズムから、これだけたくさんの動きが出てくることにも驚いた。最後はまたゴムを引っ張り、そこに体をぶつけ、弾かれ、だから何? と言わんばかりに客席を見据えて終わる。ダンサーの熱演には感心したが、1時間コンピューターミュージックを聴き続けるというのは、なかなか辛いものがある。しかし、これが作品のテーマなのだ。ダンサーも見る側も体力勝負。(5月12日モントルイユNouveau Théâtre de Montreuil)

©theresa rauter

エルマン・ディエフュイスのここ数年の作品は、若いダンサーの個性に焦点を当てて いる。この新作「Tremor and more」もそうだった。 舞台中央に4本足のどこにでもありそうな白い机がひとつ置いてある。そこに軽く腰を置いた若者の柔軟な体は徐々に硬直し、拳を握った手は震え、体を丸めて行き場のないエネルギーを抑え込んでいる。ズンズンと響くリズムに合わせて体を揺らしながら、そのエネルギーは一種の暴力となって飛び出した。それは、エキセントリックな音楽に酔いながら全てを忘れて踊り続ける若者を連想させる。興味深かったのは、作品の前半は体の一部が常に机に触れていること。そこが彼のエネルギーの根源なのか、しがらみなのか、体をくねらし、転がりながら、一瞬たりとも机から体が離れることなく動き続けている。机という限られた場所の中での動きは非常に豊かで目が離せない。最後には机から離れ、ゆったりと動くこともあったが、リズムを体が刻みながら、抑えきれないエネルギーを吐き出し続けている。そこには、希望も、絶望も、やり切れなさも、優しさも、楽しさもあり、あらゆる感情がとりとめもなく次から次へと泡のように生まれては消えていく。理屈を言われても答えられず、感情を抑えることも整理することもできないことが青春時代にはある。
踊ったのは、ジョルジュ・フェレイラ。ブラジルでのディエフイスのワークショップで出会ったという。普通の男の子だけれど、踊らせたら別人。ランコントルのHPでビデオを見られるけれど、本物はこの100倍も面白い。(5月17日CND)

©Karim Zeriahen
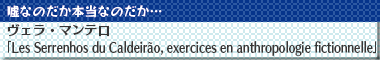
私はこの人の優しい嘘が好きだ。いかにも本当のことを語っているようで、実は作り話だったとか、そこにパロディやら皮肉を込めていたり。この作品でマンテロは踊らない。祖国ポルトガルの田舎の農民ふたりを取り上げた40年ほど前のドキュメンタリーがベースだ。田舎の、騒音のない静けさの中で人々は自分たちのリズムで、その伝統と文化に守られて暮らしている。そこからマンテロなりに失われゆく自然を語り、情に支えられた人々の生活を見せ、語る。化石のようになった木の幹を持ち上げ、抱き、歌う。その歌の見事なこと! マンテロが踊らなかったことに不満を感じている客がいることを彼女自身は知っている。だからカーテンコールで「私はダンサーだもの」と言って、それまで動かずにいたことの鬱憤を晴らすように自由奔放に踊り出した。これがまた素敵だった。踊りを期待している観客を裏切りながらも、感じていることを伝え、少しだけ観客に答える。アーティストとして、やりたいことをやり通すという精神が好きだった。(5月17日CND)

©Humberto Oliveila Araujo

白いブラウスに黒のタイトスカート、そして黒のヒール。案内係のようないでたちで、控えめに客に挨拶をしている。「ようこそ、何か問題はありませんか」前列の客の一人一人と話した後、この作品を作った経緯を話し始めた。本当か嘘か、今回はバジェットがなかったので、ダンサーを雇えず、バイブルとiPadミニだという。この作品のために作られた貴重なバイブルを客に手渡し、「回覧してくださいね。作品に興味がなければ、この本を読んでいれば良いわけで、まあちょうどいいかも」などと、ちょっとした言葉の言い回しの面白さに、ぶっと吹き出す観客多数。iPadからはメトロノームのような規則的な音を出し、それに合わせてシンプルなステップを、テンポを変え動きを変えながら続けるけれど、ここにも出てくる余計な一言にまた吹き出す。客全員に見て欲しいバイブルの回覧速度が遅いことに、少しイライラしながらのアドリブがめちゃ可笑しくて、この人は漫才師ならツッコミ役がぴったりだ。そのツッコミをさらりと言うからなお可笑しい。「37分の作品なのに、こんなことしていたらどんどん伸びてしまう。作品を伸ばすのって簡単ね」などとブツブツ言いながら、頭の上にタブレットを乗せて、パドブレまがいのステップをしながら、暗に客にプレッシャーをかけている。客にプレッシャーをかけるアーティストというのも珍しい。でもこれが面白い。頭の一部となったタブレットの画面を指でくるりと輪を書けば、メトロノームの早さが変わり、この音が延々と続くのだが、本を山積みにした上に立って、単語が並べられただけの、意味があるのかないのかよくわからないバイブルのページをちぎって口に入れ、画面に触れればなんと懐かしきビー・ジーズの「ステイン・アライブ」が軽快に鳴り響く。このギャップに爆笑。まだ続いてるわよ〜、まだやってるのよ〜と言わんばかりに、暗闇にタブレットが高く低く舞い回り、すっかりヴィノヴルスキの世界にはめられていた。(5月21日ル・コロンビエ/rencontres chorégraphiques International de Seine-Saint- Denis)

©Roger Rossell
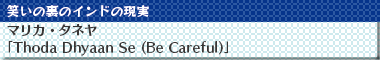
まるで小さな洋服屋に紛れ込んだかのように、カラフルな生地が規則正しくかけられている。パッと明かりが消えて、パッとついたら、そこには全裸の女性が立っていた。媚びることもなく、ただじっと前を見、ゆっくりと客席を見回している。左側の髪は刈り上げ、右側はセミロングと、インド在住の女性としては斬新な髪型をしている。髪をかきあげて刈り上げを隠したら、顔がほころび、やがて大きく笑い出した。すると、堰を切ったように言葉が溢れ出した。まるでそれまでの静かな装いの女性は存在しなかったかのように。そしてかけてあった布を体にどんどんと巻きつけていく。子供の頃のこと、父親のこと、そして彼女を守る家族のことを話しながら。インドは夜の女性のひとり歩きは危険なのだ。異性から視線を投げかけられるのは嬉しい、でも気をつけなければいけない。暴行が横行しているからだ。「この世でひとつだけ持っていけるものを選ぶとしたら…迷わず、洋服! 服が大好きなんです」と言いながら、次から次へと服を着ていく。何枚もの長いスカーフの上にタンクトップを5枚、ズボンにショートパンツにスカートにワンピース。手も口も休まることを知らない。喋り捲って着まくって、よくもそんなにたくさんの服が着れるものかと感心する。細身の体の面影もないほどぶくぶくになり、靴を履きヘルメットまでかぶって、終わり!
ただのお笑いパフォーマンスに見えるけれど、ここにはたくさんのメッセージが隠されている。インドの治安と女性の地位は守られていない。女性はたくさん服を着て、ヘルメットまで被らないと危険ということか。髪型といい、作品といい、インドではご法度なことばかり。でも、そうでもしなければ、現状をアピールできないのかもしれない。今後も応援したいアーティストだ。(5月21日ル・コロンビエ/rencontres chorégraphiques International de Seine-Saint- Denis)

©David Wohlschlag

暗闇に響く歌のような叫び声。薄暗い舞台を横切って行ったり来たりする人影が何となく見える。その影を追っていると、いきなりライトが全開。そこにはジーンズを履いて上半身裸の若い女性がいた。じっと立ち尽くし、ゆっくりとジーンズを下ろしてかがみ、「ふん、見せないわよ」とでもいうかのような表情をしながらズボンを上げた。そしてしなやかに床にうつ伏せに横たわり、まるで脱皮するかのようにするりとジーンズを脱ぎ捨てた。ゆったりと、ものすごい時間をかけて床の上を転がって移動する。うっすらと汗をかいた体はロウを塗ったかのように鈍く輝き、ロダンの彫刻を見ているようだった。すると突然両腕で床を叩き始め、やがて身体全体で床を打つ動きとなった。それは魚がピチピチと跳ねるようでもあり、自身を否めているようでもあった。声にならない喉の奥から絞り出すような声をあげる姿は痛ましものさえ感じられた。ここでふと思った、これは人魚の物語なのではないかと。希望に満ちて人間になろうとした人魚。ジーンズという殻を脱ぎ捨てて、女性になったけれど、恋に破れ、人間になることで失った声を取り戻すことも、海へ戻ることもできない。その現実は、悲しい叫びとなって体の奥底から絞り出される。 悲しみと、後悔と、 絶望。正気を失い、同じところを行ったり来たりしている。私にはそんな人魚の姿と重なった。(5月21日ル・コロンビエ/rencontres chorégraphiques International de Seine-Saint- Denis)

©Alejandro Jimenez
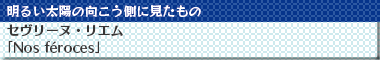
人の感覚はこうまでも違うのか。マルティニークに行って、衝撃を受けたことを題材にした「Nos féroces」。私はフランスの冬に観光気分で行ったから、南国の日差しの強さや、豊かな果物に、楽しい思い出しかなかったのだが、セヴェリーヌはその向こうに植民地化されて苦渋を舐めさせられた人々の歴史を見ていた。だから、タイトルは「残虐」だし、暗く厳しい作品だった。
まず、暗闇がかなり続いた。その中で鳴り響くのは、何かを叩いているような音。上手の赤いライトの中で数人がうごめいているのが見え始めた、そして下手では男が床に座り、置いたギターを叩き奏でている。その男の声は素敵に響いているけれど、台本は残酷だった。「殺せ!」「殺せ」。感情を殺した声が心に突き刺さる。ダンサーも踊るけれど、それはほんの少しの間で、上から吊るされたり、置かれたエレキギターをこすったり叩いたりしながら、ダンサーもミュージシャンも入り混じって叩いている。私には踊ることよりギターをいかに変わった方法で叩くかにダンサーたちが集中していたように感じた。台本は多くのことを語っているけれど、ダンスそのものからマルティニークの植民地としての苦渋や文化を感じることがなかったのは残念だった。(5月23日 Théâtre Berthelot Montreuil)

©Thierry Grapotte
|

