

Photo : Nicolas Ruel, Design graphique : Les produits de l'épicerie
今年のモンペリエダンスは、6月23日から7月7日までの会期だった。アンジュラン・プレルジョカージュがNYCBの依頼を受けて作った2作品がオープニングを飾り、モンペリエCCNの元ディレクター、現パリのCNDディレクターのマチルド・モニエが里帰りし、アバンギャルドなダヴィデ・ヴォンパクの新作「ENDO」と続いた。日本語みたいなタイトルは、寺山修司の思想にインスピレーションを得た作から。リヨン・オペラ座バレエ団は、ルシンダ・チャイルズとエマニュエル・ガットの2演目。ガットは、モンペリエダンスのディレクター、モンタナリ氏のお気に入りで、モンペリエダンスの提携アーティストでもあり、「ジャン=ポール(モンタナリ氏の名前)に捧げる」と大胆にも明言して、ふたりの仲の良さを見せつけた。これとは別に、自身のカンパニー作品を上演し、特別ワークショップも開催して、フェスティバルに大いに貢献していた。スティーブン・コーエンの新作「Pour your heart Under your feet…and walk/à Elu」は誰もが感銘を受けたと言っているし、マルレーヌ・モンテイロ・フレイタスの「Bacchantes」も素晴らしい評判を聞いている。いつかどこかで見たいものだ。
さて、今回は珍しく閉幕前の7月4日から6日まで滞在し、5日の最終プレスコンファレンスに参加した時に、モンタナリ氏が「国際フェスティバルを目指していない」と言ったのには驚いた。ダンスフェスティバルとしてはフランス最大級と評価され、世界各国からジャーナリストが集まり、著名団体から若手まで幅広く作品を紹介しているので、国際フェスティバルだと思っていた。
「地域圏統合でトゥールーズと同じ管轄になりました。トゥールーズはモンペリエより規模がずっと大きいから、そこと対抗する気はありません。それより地元を大切にしたいので、モンペリエの住民が喜ぶプログラムを組み、モンペリエ近郊の若手を育て、上演の機会を与えたいです」
意外な発言だったが、好意的に受け止めた。確かに地元に受け入れられなければ長続きしないわけで、37年間ずっと同じディレクターが仕切り、全会場ほぼ満席ということは、市や市民の支持を得ている証拠だ。バブルがはじけて不況の波が押し寄せ、助成金も企業からの援助金も減額し(BNPパリバ財団は、例年通りのレジデンス費用負担で大きく貢献)、運営は楽ではないから、いかに市民に支持され、入場料を払って見に来てくれるかが重要になる。今年初めて直前ネット限定特売をしたところ、あっという間に300席売れたという。これは大劇場の天井桟敷の席だが、不況の折、見に行きたくても高いチケットは買えない人たちが、安ければ見にくるのだということを語っている。また、一般市民が参加できるワークショップや無料の路上公演、ダンス映画の上演などを、中心地だけでなく、住宅街などの少し離れた場所を日替わりで移動しながら開催するのも、ダンスが身近にあることをアピールする良い手段で、どこも多くの人で賑わっていた。地元重視のプログラムとはいえ海外の大カンパニーから新人まで幅広くプログラムを組み、プロから見ても食指が動く内容で、37回目のフェスティバルは盛況に終わった。来年の予定もちらりとほのめかし、さらに39回目の再来年、そして40回目のプロジェクトにも意欲を示して、モンタナリ氏のフェスティバルは安泰しているとアピール。
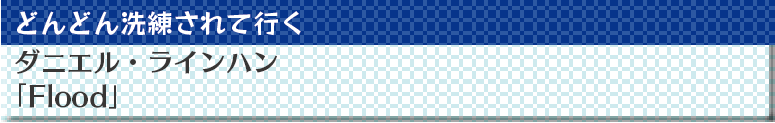

©Jean Luc Tanghe
2008年にランコントルでラインハンのソロ「Not About Everything」を見て、変わったやつだなあと思っていたが、その独自のセンスがどんどん洗練されている。 「Flood」は、前作の「dbddbb」の路線で、シュワッ、キー、ブブブ、アウゥ~、オ? オ? などの奇声が飛び交い、噛みつきあったり、遠隔操作や催眠術をかけたりと、遊びのような戯れがマンガチックで愛嬌がある。 4枚の薄い白い布が吊るされた美術は、その中に入れば姿が少しずつ薄れていき、4枚目では見えない。この布の中を出たり入ったりしてミステリアスな面と、言葉にならない叫びと遊び的な動きのおふざけが妙にマッチしている。動物的本能で行動しているような人たちの動きに合わせた奇声と、予想もしない方向に展開するシーンに、軽い笑いが客席のあちこちから聞こえる。合図が鳴ったら、それまでの展開をスピードアップして再現し始めた。繰り返しのたびにスピードアップして、これが4回も繰り返されればこちらも動きを覚えるわけで、早送りの滑稽な動きや即興的な反応に笑いが漏れる。ふと気がつくと、黒ベースの服にビビッドカラーのアクセントや装飾のついていた衣装がだんだんシンプルになっている。そしてホリゾントからのライトの逆光の中での慌ただしい踊りの後、いつの間にか白ベースの衣装になって静かに踊っている。黒から白へ、動から静へ、おふざけのようで真面目で、みんな仲良しの微笑ましい終わりが気持ち良い。作品の作り方や美術が、ずいぶん洗練されたと感じた。(7月4日アゴラ・バグウエイスタジオ)

©Jean Luc Tanghe
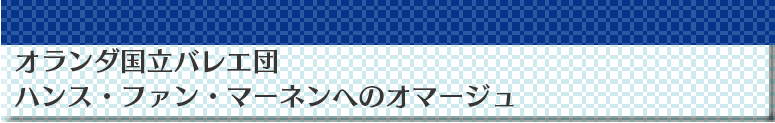
大劇場での締めは、オランダ国立バレエ団によるハンス・ファン・マーネン5作品が2夜に渡って上演された。初日の第1プログラムは「Adagio Hammerklavier」、「Two Gold Variations」、「Sarcasmen」、「Frank Bridge Variations」、2日目の第2プログラムは、「Metaforen」、「Adagio Hammerklavier」、「Sarcasmen」、「Frank Bridge Variations」。
「Adagio Hammerklavier」は、幕が波打つ映像の下で、スカイブルーのワンピースの女性と白いタイツ姿の男性の3組のカップルが、ピアノの生演奏に合わせて踊る。大きく揺れるカーテンの動きが、踊るダンサーたちの心を表しているようだった。
「Two Gold Variations」は、14人のダンサーによる作品で、総出演の大群舞からデュエットまで多彩な変化に富んだ見応えのある作品。特に男性の踊りが力強く、テンポのあるムーブメントと展開にただただ見入るばかり。ここには、奥村彩と山田翔が出演していたが気がつかなかった。ということは、バレエ団に完璧に溶け込んでいるということだろう。

「Adagio Hammerklavier」©Hans Gerritsen
「Sarcasmen」は、男女の掛け合いが面白い。女の気を引こうとして、一生懸命踊る男。それをシラーっと腕組みして見ていた女は、男の手をするりと抜けてひとりで踊り出した。ようやく女を捕まえたところで、なんともちぐはぐ。男もさすがに堪忍袋の尾が切れたのか、女を批判し始める。ピアニストはふたりの関係など知ったこっちゃないという反応で、3人のチグハグな関係をコミカルに描いた。
「Frank Bridge Variations」は、男女5組による作品で、統制のとれた構成と、動きの流れの美しさを見せる洗練された作品だった。
「Metaforen」は、 鏡に映ったようなシンメトリーな構成と、モノトーンでシックにまとめた衣装と美術が印象的。また、男性ふたりのアダジオが美しく、ほれぼれした。音質を細かく分析して振り付けているのが非常に心地よい。

「Sarcasmen」©Angela Sterling
アカデミックで非常に均整のとれた作品を創るハンス・ファン・マーネン。85歳の現在でもオランダ国立バレエ団のトップとして、75人のダンサーを指揮している。1965年から2005年までの作品を今回上演したが、バラエティに富んだ組み合わせで、ファン・マーネンの幅広い振り付けを満喫した観客のリクエストで、長いカーテンコールが続いた。この公演後に行われたレジオンドヌール・コマンドゥール(勲3等文化勲章)の受賞式では、長い祝辞にあっさりと「ありがとう」の一言だけ。公演後に正装して立ち続けているダンサーをいたわって、そしてカクテルに早く手を出したい招待客の気持ちをしっかり読んで、その人柄にまた盛大な拍手。(7月4、5日コラム・オペラベルリオズ)

「Frank Bridge Variations」©Angela Sterling
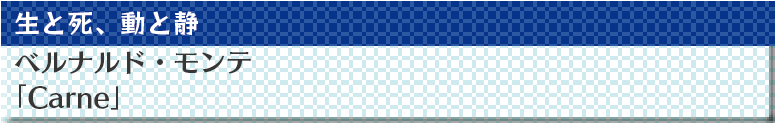
小川のせせらぎが聞こえ、藁が敷きつめられた場所で、じっと手を見つめる人。死者が蘇ったのか、輪廻転生か、床がゆっくりと盛り上がって人が現れた。何かに憑かれたように激しく踊る人、じっと動かない人、ひとつの場所でそれぞれの人生が浮き上がる。静と動、生と死。マルタン・グサンドが撮った原住民の写真に触発されて作ったという。日常に死があり、宗教があり、それに基づく儀式があった。神と近く、トランスに入って神の言葉を聞いた時代。ただ、これを作品にするには焦点が絞りきれず、少し幅が広すぎたように思った。分かりそうでわからない、そんなもどかしさが残った。(7月5日Théâtre la Vignette)

©Didier Olivré
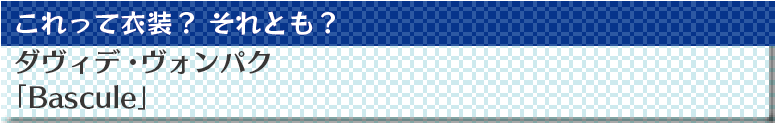
新作にも興味はあるけれど、その昔はどんな作品を作っていたのかも知っておくべき。今から12年前の作品を見るのも悪くないと、「Bascule」を見た。2005年、ノンダンスが語られるようになった時期の作品だ。
規則的なドラムが繰り返され、赤いシャツを着た女性がリズムに合わせて口をパクパクさせたり、目をキョロキョロさせたり、首を動かすだけの動きが延々と続く。しばらくして位置を変えてまたキョロキョロ。そこへ黒いショートパンツを履いた男性が出てきて、これまた誰にでもできそうな簡単な動きを繰り返すだけ。今度はなんと、全裸の女性が出てきた。おお大胆な! そしてまた簡単なエクササイズのような動きをしている。と、あれ? さっきまで裸だった女性がいつのまにか緑のレオタード姿になっているし、男も緑のTシャツを着ている。あら不思議、いつ着たの? よく見れば、体の凹凸が白いリノリウムにはっきり見えるではないか。全員が全裸だということを分からせるような振り付けをタイミングよく入れて、カラクリを見せてくれるところが憎い。多くの人も気がついて、会場はざわざわ。全て計算済みで、見る側の心理を深読みしているのは、さすがで抜け目がない。最後まで単調なリズムに単調な動きだけれど、これまたタイミングよく動きと構成を変えて、ノンダンスのくせに盛り上げる。カーテンコールは塗料と同じ色の服を着て。細かい気遣いがなんともうまい。
昨年KYOTO EXPERIMENT京都国際部隊芸術祭でめちゃ受けして、フランスより日本で受けているというのが現地情報。京都のアバンギャルドさは、世界のトップレベルかも。 (7月6日アゴラ・バグウエイスタジオ)

©Marc Coudrais
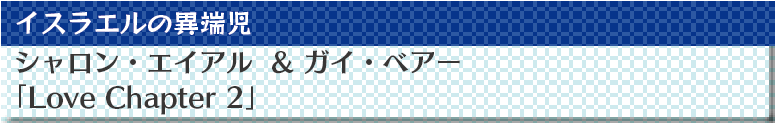
70年代からずっと世界をリードしている振付家の元で踊っていたダンサーたちの活躍が、ここ数年特に目につく。イリ・キリアンに見出されたポール・ライトフットとソル・レオン、ウイリアム・フォーサイスのバレエ・フランクフルトにいたクリスタル・パイト。そしてシャロン・エイアルはオハッド・ナハリン率いるバットシェバ舞踊団に25年いたという。彼らのそれぞれが、師から得たものを肥やしに独自の世界を築いていて、これからのダンス界を引っ張って行くのだろう。
「Love Chapter 2」は、昨年モンペリエダンスで上演した「OCD Love」の続きとも言える作品で、人生の暗い部分をさらに追求したという。
規則的なリズムの中、6人のダンサーのシルエットが浮かび上がり、ゆっくりと手や足を伸ばしている。その中で両腕の力こぶを震わせて強さを見せる人や、殴るような動きが見える。強者と弱者、富と貧困、権力とそれに支配されるものという対極は、現社会への痛烈な批判だ。ユニゾンのようだけれど、それぞれのダンサーのニュアンスが違う上、ジェスチャー的な動きをアクセントにしながら暗に出来事を想像させる手法ゆえ、連想が膨らみ、多くのメッセージが感じられる。
どこにいても常にインスピレーションを受けていて、この作品では愛と孤独をテーマにしたというエイアル。動きのボキャブラリーは豊富なので、ダンサーに作らせたのかと思ったら、驚くことに、全ての振り付けはエイアル自身によるもので、ダンサーに即興をさせることはないという。まずエイアルが動き、それをダンサーが見て覚え、その中からコンセプトを見つけて深めて行くのだという。そんなに簡単に振りを覚えられるものですかという質問に、エイアルは笑って「ダンサーが素晴らしいですから」の一言。また、ダンサーはテクニックと感情が繋がっているので、テクニックと表現が同時に進行しながら作品が出来上がるのだという。自身の動きを見せるのは、それが自分の表現だからときっぱりいう。「何かを見て感じ、その中のいくつかの要素が自分の中で混ざり合って出来上がる。音楽は大好きで、人生をも変えるもの。ガイ・ベアーと長年コラボレーションしているが、それぞれ独立して仕事をしている、ガイとは全く違うから。」などと、意外な発言が飛び出したトークだった。イスラエルの新たな嵐に要注意。(7月6日Opéra Comédie)

©Gil Shani
|

