

©Alain Scherer
アリ・モワニはイランからフランスに移住したアーティストで、その思い出を綴った「Lives」が印象に残っている。哀愁というよりハードなドキュメンタリー的な作風で、戦争を体験した痛みと、祖国を捨て家族と別れた苦悩が伝わる作品だった。新作「man Anam ke Rostam Bovad Pahlavan」も「Lives」同様ワイヤーを使い、金属のパーツを組み合わせた人形との共演で、一見軽そうに見えたのだが、最後にぐさりときた。
明るい照明の下でモワニは体にワイヤーを取り付けている。これが開場時で、何気にカラクリを見せている。彼の動きは対面にいる人を模した金属の人形と連結していて、モワニが左手をあげると、人形も左手をあげる仕組みだ。客電がゆっくりと落ちて、微妙に体の中心を動かしていたが、いきなり両手を広げて前傾姿勢になった。もちろん金属の人形も同時に同じ形をとる。モワニの動きはホリゾントの前につり下がった銀色の重石のようなオブジェとも連結しているので、モワニとは別の動きが背景で鈍い光を放ち、波打っている。ノイズ音や金属音の中、人間と金属のユニゾンは動きの幅が広がれば広がるほど面白く、人形なのに腰の動きや手首足首の微妙な動きが色っぽい。頭に当たる金属が取り付けられればなおさら命がある人間のようで、スピードがついてくるとワイヤーの伝達率の遅れの影響で、モワニの動きとブレが出て面白いし、モワニも「ちゃんとついて来いよ〜」と声をかけるかのように人形を見ながら楽しそうに踊っている。モワニの優しい顔に安心して踊る人形。しかし、この遊びは続かない。人形の目を盗むようにして黒い箱を引き寄せ、腕を優しく掴んで、赤い肉片を結びつけていくモワニ。腕に、足に、肩に、頭に。そしてその度に人形の関節を外していく。その途端に張力を失った金属の棒は中途半端な位置で止まる。それでもワイヤーは連結したままだから、モワニが右手を上げれば右手だった部分が同じように動く。しかし、もはや人形の形をしていないから、ただの金属の棒として意味のない動きでしかない。そしてモワニが自分の体についていたワイヤーをひとつずつ外していくとホリゾントに浮かんでいた重石が勢いよく床に叩きつけられた。鋭い音がして見れば、キラキラと輝くオブジェは水が半分ほど入った透明のペットボトルだった。パーティは終わり、現実だけが目の前に広がっている。不思議な光を放っていたものは何の変哲もないペットボトルとなって床に転がり、人形の体は赤い肉片をぶら下げたまま、金属の棒となって宙に浮いている。それは爆撃か銃か、あるいは拷問によってズタズタにされてさらされている屍を想像させた。
ペルシャ神話に登場するイランの英雄ロスタムにインスピレーションを得て作品を作ったという。「ロスタムがいたからこそ今の自分がいる」という意味のタイトルは、戦いの生涯を送ったロスタムの精神は受け継がれ、人の歴史はロスタム同様に殺し合いを続けながらしか作られないということなのだろうか。(11月22日 Théâtre de la Cité International/New settings/Fondation d’entreprise Hermès)
エルメス財団企画によるニューセッティングズは、コンテンポラリーアート集団をサポートしているので、興味のある方はホームページを見てください。

©Alain Scherer
http://www.fondationdentreprisehermes.org/Savoir-faire-et-creation/Arts-de-la-scene/Programme-New-Settings


©Rosa Frank
真っ赤なシャツを着たライムントがズボンを捲り上げて横たわり、ピアニストがモーリス・ラヴェルの「ラ・ヴァルス」を丸々一曲弾く。怒っているかのように鍵盤を強く叩き、不愉快な音の後に綺麗なメロディが流れるという奇妙な旋律の中、ライムントは微動だせず、ただピアノ曲が流れるだけだった。ピアニストは曲を弾き終えれば、さっさとピアノをしまい、ライムントは起き上がって袖に引っ込んでしまう。空になった舞台にグレーの布で体を覆った人たちがゆっくりと現れた。一団となって感情もなく、ただゆっくりと歩いている。折りたたんだ布の上に座り、遠くを見つめる集団。救急時に使う金色の保護シートに体を包み、ジョウロで水をまき、赤いバラを差し出す。いつも通りにバラエティに富んだジャンルの曲が流れ、ダンサーのソロが続く。演歌の代わりに韓国の伝統音楽が流れ、今回初参加のJi Hye Chungが優雅な韓国舞踊を披露したほかは、いつものお気に入りダンサーたちによる前作と同じような流れだった。マリオン・バレステの出番がもっとあっても良かったように思ったが、エマニュエル・エゲルモンは静かながらも小気味好くキレのある動きをし、上野天志はしなやかな動きの中にコケティッシュでハリのあるダンスを見せてくれた。音楽が体から出ているように踊る姿はいつ見ても心地よい。特別ゲストのオルネラ・バレストラは、客席に向かってゆっくり歩くだけなのに、観客を引き付けてしまう存在感。圧倒的だった。とりとめもなく流れていくように見えるのに、終わってみると何かが心の中に残っている。それは孤独であり、悲しみや喜びでもあり、生きることへの希望とも取れた。冒頭のライムントが横たわっていたシーンは、世界中に配信された子供の溺死体、戦火を逃れて地中海を渡る途中で難に遭い、岸辺に打ち上げられた子供の姿だったのだ。着の身着のままで国を捨て、与えられた布で寒さをしのぎ、平和の地を求めてひたすら歩き続ける難民たち。絶望と希望の間で、それでも希望を捨てずに生きることを望んだ人々。
切迫して訴えるのではなく、さらりと状況を見せて後は観客の想像に任せるけれど、ライムントの意向はちゃんと伝わってくる。出演者によると、作品の大雑把な趣旨の説明は受けたけれど、それ以上の詳細は伝えられないまま初演を迎えたという。ダンサーに深い感情を持たせずに演じさせることで、押しつけがましくならず、それでいてちゃんと作品の意図を伝えている。ダンサーを自由に泳がせながら、ピシッと仕切るあたりがうまい。(11月23日ポンピドゥー・センター)

©Rosa Frank
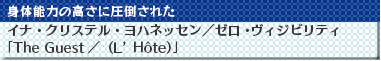
モザイク模様の床を四角く囲む客席。いくつかの丸い椅子が四隅に置かれている。照明機材は低いところにあるので、劇場というより、閉ざされた室内というイメージだ。四角いライトが舞台を照らし、黒い服のダンサーたちがひとりずつ出て来て、ミキサーの方に向いて立つ。全員が揃ったかに思われた瞬間にその構図は崩れ、足を高く上げながら激しく踊る人や、男を倒す女など、それぞれの動きが始まる。客に向かって突進したり、髪の毛で顔を隠した女性が宗教儀式のように踊ったり、椅子を倒しては元に戻す人や、その椅子の上を歩いたり、トランスに入ったかのように身体中を震えさせたり。照明は不安定に流れ、落ち着きのない人たちの不安を煽り立てる。黒服の一団が風の如く去ると、今度は普段着のダンサーたちが演じ始める。コンピューターのエレクトリックな音の中、肩を組んで歩いたり、男同士でキスしたりと、日常の風景が描かれる。
パート1の黒い衣装のシーンでは不安や暴力性や信仰などの精神的なものを表し、普段着のシーンでは、日常のどこにでもありそうな風景を描くことで、内面との対比を見せた。望むと望まずに関わらずやってくる人と出来事。招待客なのか招かねざる客なのか、出会いがあり、関わり、そこを通りながら毎日が過ぎていく。
非常によく鍛えられたダンサーたちで、身体能力の高さと疲れ知らずのエネルギーに飲み込まれた。また、四方に客席を設けた正面のない舞台の使い方が上手く、どの面から見ても構成の面白さがわかる作りになっている。また、唯一の小道具の何の変哲もなさそうに見えた丸い椅子が、向きを変え位置を変えることで重要な意味を持たせる美術に早変わりした演出は見事。(11月25日Le Monfort)」

©Erik Berg
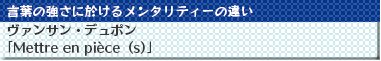
ヴィジュアル的に印象深い作品を創っているヴァンサン・デュポン。今回も面白い展開を見せてくれた。
いきなり舞台に明かりが入って目に飛び込んできたのが、三角形のモノトーンなスペース。一瞬の暗転の後、同じスペースに黒服をまとったダンサーがひとり。下手のグレーの幕に沿って手を細かく動かしながら進んでいく。ズン、という音と共に暗転になり、しばらくした後に先ほどと全く同じ光景となった。ダンサーがひとりたたずんで、それから同じ振りを繰り返す。デジャヴのようだが、今度は先ほどより強いズンという音で暗転。明かりが入るとふたりになっていて、先ほどの人は同じ動きを繰り返し、もうひとりは別の動きをしている。エコーの聞いたズーンという音で暗転になった後。今度は3人に、そして4人に、最終的には5人になってと、暗転のたびに人が増え、繰り返される動きが増幅し、彼らの息遣いがこだまするように舞台を埋めていく。そして突然落下したグレーの幕。むき出しの舞台で冒頭のシーンが繰り返され、暗転の間と幕の後ろのダンサーの動きが種明かしされる。「ここまでのことはプロローグでしかない」「あなた方は何も見ていない」「いつものことを期待しているとすかされる」と表情のない電光掲示板の文字が流れ、今私が見ているものはバーチャル、あるいは自分のフィルターを通して勝手に理解していることだということなのだろうかと、次に起こる出来事を待っていると、たくさんの黒光りするボールが降りてきた。下手に置かれた透明板のハンドルを操作すると、無数のボールが上下する。これも幕が落ちる前に見せたミステリアスなボールのダンスのカラクリを見せたのだ。不思議なことなどひとつもない、全ては操作され、そうなる理由に基づいているとでもいうようだった。ボールのひとつを弾くと、連鎖反応で不規則な動きをし始める。これも科学の原理であって、不思議なことでも何でもない。作品は作られ操作されたもので、神秘などあり得ないとでもいうかのようだった。
ここまでは面白かったのだが、後半にダンサーがせわしなく動き、短いセリフを発したときに冷めてしまった。電光掲示板の得体の知れない冷たさが、人の声となって響いた瞬間に温かみが生まれ、現実の世界に引き落とされた感じで、それまでのヴァンサン・デュポンの温度のないミステリアスな作風が押し付けがましい哲学になってしまった感があった。ただ、演劇大国のフランス人にとっては言葉によって作品の意味が深められたようで、演劇出身のデュポンのセリフ選びのうまさが評価されていた。(11月19日アベス劇場)

©Marc Domage

19世紀に人気を博したロイ・フラーの布を大きく振った作品にインスピレーションを得た作品で、3つの布が不思議な形を作る造形美に見入った。
黒服の女性3人が、舞台の上でゆっくりと黒い布を広げている。いつになったら布が舞うのだろうかとじれったい気持ちで見ること数分。3人がそれぞれの方法で布の中に滑り込み、アトランダムに歩き始めた。時々響く奇妙な音。それは喉を鳴らしたり、発した小声を吊るされたマイクが拾っているのだと気づくのに少し時間がかかった。舞台をゆっくりと歩いていた3人の姿が消えゆく照明の中でシルエットとなり、形を作り、布を回す。風を切る音が増幅し、流線型のシルエットが次々と形を変え、3人がひとつの形をつくれば、動物になったり物体に見えたり。明かりが戻ったところで、多様に変化する布とシルエットの変容を見せ、暗転の後も音だけを聞かせて終わる。微妙な照明の変化と、増幅させた音を使った現代のロイ・フラー。天から見て微笑んでいることだろう。(11月22日Théâtre de la Cité International/New settings/Fondation d’entreprise Hermès)

©Martin Argyroglo
|

