


©塚田洋一
2015年の横浜ダンスコンペティションで若手振付家のための在日フランス大使館賞を受賞して、6ヶ月のフランス滞在をした川村美紀子。その成果が気になって見に行った。と言っても出発前の作品を見ていないし、フランスでもすれ違わなかったので、渡仏前/渡仏後の比較などできないのだが。
プログラムには「フランスにいた半年間、何もしなかった。朝起きて、大きく息を吸って、ご飯食べて、軽く身体を動かして、日向ぼっこして、散歩して喋って、寝る」と書いてある。自費留学ならともかく、フランス政府からお金をもらって滞在する身でこれをしたというのはなかなかの度胸の持ち主と見た。普通なら後ろめたさを感じるものだ。まあ、何もしないと言っても半年で6箇所のダンスセンターをまわり、その間に4回のパフォーマンスやワークショップの場が用意されていたというから、それなりのプログラムをこなしていたと思う。CCNグルノーブルのディレクターにこれでいいのかと聞けば “nothing is someting”という返答。芸術家は好きなようにさせないと育たないと考えるフランス人らしい答えだ。フランスは川村に合っていたのだと思う。その寛容さに包まれて、日本では得られないものを得てきたようだ。
さて、日本初演の「地獄に咲く花」は、般若心経の帯が遠近法で吊るされ、舞台奥に続く一本の白い線の上を、薄手の布を体にふわりと巻いた川村が、背を向けたままゆっくりと奥へ進むシンプルな構成だった。白い線は川村の動きによって崩され、かき消され、それは過去を消しているようにも、決められた運命の道を自ら壊していくようにも見えた。ほとんど後ろ向きでゆっくりと進んでいくだけの構成なのに、立体的な空間が見えたのと、気負いのない踊りに好感を持った。
作品とは、振付家の体験や思想をひとつの物語として描き、その架空の世界をいかにリアリティーを持って見せるかが、観客の共感を呼び、作品に引き込むかどうかの決め手になるのだと思う。それは身体的要素によるときもあれば、テーマによることもあるし、実際にはありえないことだとわかっていても、迫真の演技に引き込まれたりと、それは受け止め方による。ただ、舞台は透明のガラス張りの空間なので、作る側や演じる側の迷いやしたたかさは見えてしまうし、それがなくとも演じる側の体調やほんの一瞬の集中力の欠如までもが見えてしまうデリケートな空間なので、その日の出来に左右されることがあり、一度見ただけで判断するのは避けたいと思っている。
この日の川村の踊りは、頑張って作って踊っているわけでも、何かを訴えようとするのでもなく、日本で生まれて生活をしてダンスをして、賞をとってフランスに行って帰ってきただけの素直で気張らない肉体を感じさせ、それがとても自由で解放されていて心地よかった。
これからさらなる経験を積んで変わっていくだろうが、フランスでの体験を忘れずに、自分のペースで今後の活動を続けて欲しいと思う。(2月4日ヨコハマダンスコレクション ダンスクロス・アジアセレクション 横浜赤レンガ倉庫1号館)

©塚田洋一


「マッチ売りの話」©Kishin Shinoyama
斬新な作風で精力的に活動している金森穣率いるNOISM。今回は、 NOISM 1による「マッチ売りの話」と「Passacaglia」の2本立て。
まず「マッチ売りの話」は、アンデルセンの童話と別役実の同名の戯曲をベースにしていると言うが、別役版の要素が強かったように感じた。舞台の中央部分を老夫婦の住む部屋に見立て、その周りを回廊のように街路が設定されていて、装置を移動することなく瞬時に場面転換できる構成は、ふたつの世界を見せるのに効果的だった。
義父により7歳の少女は真冬に道でマッチを売らされ、挙げ句の果てに暴漢に靴まで奪われてしまう。横に立つ娼婦にも罵倒され、金を稼げない少女は義父からの暴力にも耐えなくてはならない。一方、食卓の用意をする質素な老夫婦の暖かい部屋に寒風が舞い込み、若い女とその双子の弟の突然の出現に困惑する老夫婦。
この作品には三面記事で目にするような社会問題がぎっしりと詰まっていて、下手をしたら重くて暗いイメージになりがちなところを、ダンサー全員が面をつけ、ジェスチャーのような動きで綴ることでおとぎ話の域を出ないようにさせた演出は面白いと思ったし、外での出来事と家の中の温度差が感じられる構成もよくできている。シーンごとに音楽を変えることでメリハリをつけてはいたものの、時々それが説明過多に感じられることがあり、もう少しスッキリできるのではないかと思った。
最後に精霊役の井関佐和子が全てを丸く収めるが如くに美しい踊りで皆を和ませ、出演者たちは淡々と舞台上の小道具を片付け、いつの間にか別世界の「Passacaglia」になっていた。
まるで夢を見ているように始まったこの作品は、金森が目指した通りの一筆書きの作品。ムーブメントは止まることを知らずに果てしなく広がり、構成も川の水が静かに流れる、あるいはまさに筆が延々と線を描き続けるかの如くで、自分がその流れの中にいるような心地よい感覚に浸った。ただ、終わってみるとふたつの異なる作品が続いたことで、前の作品の終わりが曖昧になり、スッキリとした気分にはなれなかった。社会問題を含んだインパクトの強い「マッチ売りの話」を終えた後に短い休憩を設け、新たな気持ちで「 Passacaglia」を見る。ありきたりの手法かもしれないが、私にはこちらの方がそれぞれの作品を印象付け、しっくりくるように思った。(2017年2月11日彩の国さいたま芸術劇場)

「Passacaglia」©Kishin Shinoyama


「道成寺」©エー・アイ(Naoto Iijima)
女の執念を描いた能作品を2作、「狂」と総称して「道成寺」と「金輪」をコンテンポラリーダンス版に仕上げ、特殊な舞台の能楽堂で上演した遠藤康行。
「Dojyoji+」では、女の狂気とも情熱ともいえる念を描いたという。冒頭の津村禮次郎の張りのある踊りに背筋がピンと伸びる。その圧倒的な存在感、そしてキレがあり正確なポジションに入る踊りに見入っていると、まるで津村の踊りが風を巻き起こしたかのように敷かれていた銀色の布は波のように膨らみ、そこからダンサーたちが現れた。床を這うように動いていた塊がやがて立ち上がり、松明の炎が飛び散るように広がり、激しく踊り出す。女の燃え盛る情念が舞台を駆け巡っている感じだ。プログラムにも書いてあるように、物語を追うのではなく、女の執念に焦点を当てていて、津村と女性6人のダンサーが情念の塊となっている。男(上田尚弘)は、その念に巻き込まれながらも自己を守り、能楽堂舞台の太い柱と一体化するように身を隠し、逃れようとしている。下手の袖からの強い光は反対側の壁に大きな影を残し、嵐の後、あるいはその前兆を表すかのような不気味な静けさが舞台を覆う。能舞台を効果的に使った照明と出入りは、女の複雑な感情の変化を引き出し、それは各ダンサーの特徴を十二分に生かした振り付けにもよるところで、見応えのある作品に仕上がっていた。
これに対し「KANAWA」は、恐ろしい情念というより、お互いをいたわりあうような優しさが印象に残り、原作にあるような本妻の恨みや、身代わりの人形との激しい戦いなどを期待していた私には、あっけなく終わった感があった。それは、酒井はなの優雅な踊りと少し線が弱いように感じた梅澤紘貴の踊りによるものかもしれないし、「影」の使い方にもよるのかもしれないが、能作品とは異なる視点からのアプローチは新鮮に感じられた。ただ、座る席によって印象がかなり違い、「Dojyoji+」に比べて全体の構成が単純なように思った。(2017年2月17日セルリアンタワー能楽堂)

「金輪」©エー・アイ(Naoto Iijima)

横浜ダンスコレクションの後はTPAMが続き、横浜界隈は面白い展開をしている。世田谷シルクは演劇なのだけれど、昨年アヴィニヨンの路上で見て興味を持ったのでちょっと紹介を。
フランスではダンス、ヌーボーシルク、演劇の垣根が低くなっていて、ダンスを見に行ったらダンサーがセリフを喋り、演劇を見に行ったら言葉が一言もなかったりするし、ヌーボーシルクは劇場によって演劇のジャンルになっていたりダンスだったりと、ジャンル分けすることが難しくなっている。その名前からヌーボーシルクだと思っていたのに、アヴィニヨンでは白装束でダンスパフォーマンスをしていた世田谷シルク。では劇場では何をするのかしらと見に行った。
「跡」は、ダイニングと居間の小さな家に住んだ男の一生を描いている。這い這いの赤ん坊が大きくなり、反抗期を迎えた姉が家出をし、初恋に敗れた苦い青春の後にめでたく結婚をして家庭を築く。母親の死、そして年老いたある日に聞こえた花火の音に一気に青春が蘇る。そして誰もいなくなった部屋。そんな男の一生を、無言劇に仕立てていた。
「こんこん」は、いつもと変わりない朝を迎えたはずの男が、自分以外の人間が全て狐になっていたという悪夢から逃れようとして、すってんころりん穴に落ちてタイムスリップ。鶴ならぬ狐の恩返しに浦島太郎、桃太郎の昔話も織り込んでのファンタジー作品。落語も操り人形もあってなかなか楽しい構成になっていた。セリフが続くので演劇作品だけれど、動きが多く、声を交えてのユニゾンもあって、視覚と聴覚を刺激してくれる。場面転換はいたってシンプルな四角い枠が別世界への入り口、壁、玄関になり、流れを止めないテンポの良い展開にあっという間に時が経った。
何でも可能な現代では、ジャンルにこだわらずに必要な要素を取り入れ、グローバルな視点からテーマを描き、いかに観客を共感させるかがキーポイントになるのではないかと思っているのだが、この公演がまさにそれだった。また、英語の字幕をつけての上演という心配りと動きの多い構成は言葉の壁を超えたようで、今回の上演で海外からのオファーがいくつか来ているという。経験を地道に積み上げ、海外との交流がこうして広がって行くことが嬉しかった。(2017年2月18日さくらworks関内/TPAMフリンジ参加作品)




©Littre Shao / Opéra national de Paris
すでに何本かの作品をパリ・オペラ座バレエ団に振り付けしているウエイン・マクレガーが、自身のカンパニーとオペラ座のダンサーを交えての作品に挑戦した。
暗転の中で始まった陽気なパーカッションに合わせて、たくさんの丸いライトがクネクネと動き出した。衣装にライトが施されているのだ。この一連の踊りが終わると、一列に咲いたメタリックな花が万華鏡のような模様を見せる。花が喋っているようにも見えるし、色のせいか官能的な不思議な世界を見せている。これがダンサーの腕を利用したものだとわかる頃に場面は転換し、ダンサーたちの踊り三昧が始まった。マリー=アニエス・ジロ、ジェレミー・ベランガール、セバスチャン・ベルトー、リディ・ヴァレイユ、ルーシー・フェンウィック、ジュリアン・メイザンディの6人のオペラ座のダンサーと、マクレガーカンパニーの9人のダンサーによるコラボレーション。作品自体は2015年初演だが、今回のためにオペラ座改訂版となった。マクレガー作品を知り尽くしているカンパニーメンバーに引けを劣らぬオペラ座のダンサーは、スピーディで難しい動きをよくこなしている。特にジロ、ベランガール、ベルトーの動きが目を引いたが、オペラ座のダンサーにはエレガントさを、カンパニーメンバーには力強さをといったような、それぞれの特徴を生かして個性を十二分に引き出していたマクレガーの手腕によるところが大きいと思う。カンパニーメンバーの高瀬譜希子も非常に良い踊りをしているのが印象に残った。
エネルギッシュな動きだけでなく、美術も多様で、モノトーンからカラフルな色使いの大胆な美術、客席を照らすスポットや、大きな鏡を利用して奥行きをさらに深めた三次元的美術がマクレガーらしく、オペラ座のようでオペラ座ではなく、マクレガーカンパニーとも少し違う雰囲気が新鮮で、この二つのカンパニーのコラボレーションは成功裡に終わったといえよう。(2月22日オペラ座ガルニエ宮)

高瀬譜希子 ©Littre Shao / Opéra national de Paris


©Jean Couturier
1月のアパラタスでのアップデイト公演を終えた後フランスに渡り、ナントでのラ・フォルジュルネ、マルセイユ近郊のマルティーグでの新作に続いて、パリ・シャイヨー劇場での新作、終われば日本にとんぼ返りしてオペラの「魔笛」と、休むことを知らずに活動をしている勅使川原三郎。次々と新作を生み出す能力と踊り続ける体力には脱帽だが、本人はいたってクールで、やりたいことができて非常に満足とばかりに明るい顔をしている。
アップデイトもナントもマルティーグも見逃してしまったが、パリ公演はゲット。
2015年に藤倉大とのオペラ「ソラリス」での共演を機に、その音楽性に魅了された勅使川原が、シャイヨー劇場のための新作「Flexible Silence」で再びアンサンブル・アンテールコンタンポランとコラボレーションをした。前半は円、そして暗と明をモチーフにしていて、 中央に位置した演奏家5人が弧を描いて並び、その前にひとつの中に濃淡の円が重なる3つの円が浮かび上がっている。そこにものすごいスピードで飛び込んできた黒い影。小さなコウモリのようにせわしなく向きを変えながら舞っている。黒い衣装のひとりがすっと闇に消えると同時にもうひとりが現れて、光を楽しむかのように舞った後、また闇に吸い込まれて消えてしまう。いつの間にか床を照らしていた円は濃度を変え、位置を変え、闇に住む人たちの異なる世界を描き出す。闇にはそれぞれの色があり、温度も違う。一人が二人になり、時に揃いの踊りとなり、散っていく。疾風の如く過ぎ去ったかと思うと、吹き溜まりに残されたかのようにゆったりと動き、光の中で体のあらゆる部分が別の方向に流れるような流れに反する予測不可能な動きに目が離せない。ある一瞬、佐東の姿が宮田佳に重なった。以前勅使川原が宮田は下に落ち、佐東は上に上がるダンサーで、全く異なると言っていたのに、なぜ宮田の姿が重なったのか。それは、これこそが勅使川原独特のムーブメントで、佐東がそれをしっかり身につけた証拠なのだ。前半が円だったのに対し、後半は四角い空間の中での勅使川原と佐東のふたりによる踊りだった。
物語があるわけでもなく、交響曲のような美しいメロディーが流れるわけでもない作品に観客を1時間40分という長さを引き付けるのは並大抵のことではないが、大舞台だからできる照明や、演奏家とのコラボレーションとダンサーとの位置関係など、構成演出が非常によく練られていた。勅使川原独特のムーブメントはいつ見ても新鮮だし、佐東の空気の中を泳ぐような動きには目が離せず、ふたりの時間軸に変化をつけた動きのボキャブラリーの多さには感心するが、非常にデリケートなパートであるがゆえに、特に後半のダンスは大きな客席には少し繊細だったように思った。(2月23日Théâtre national de Chaillot )

©Jean Couturier

ランコントル・コレグラフィック
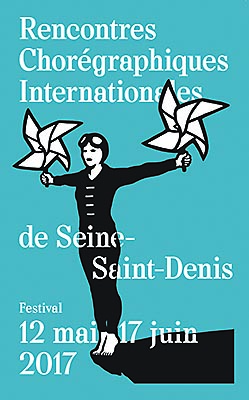
フェスティバル・ランコントル・コレグラフックは5月12日から6月17日までで、パリの隣の93県の12劇場で29人の振付家作品が上演される。ディレクターがアニタ・マチューになってかなりの年月が経つが、振り返ってみるとここから世界に羽ばたいて行った振付家が多いことに気がつく。上演当時は物議を醸し、これがダンスか? などと悪評を叩かれていたのに、数年後にはツアーをして周り、注目度の高いアーティストになっているところを見ると、アニタ・マチューは先見の明があるということになる。時代を先取りしすぎて周りがついていけないわけで、前身のバニョレ国際振り付けコンクールほど派手に注目を集めていないけれど、実はものすごくアバンギャルドなフェスティバルなのだと思う。
今年のプログラムにざっと目を通すと、まだ見たことのない振付家の名前が多いので、これといったお勧めはできないのだが、エルマン・ディエフュイス、ヴェラ・マンテロ、トーマス・ハワート、ダニエル・ニナレロ、クビライカーン・アンヴェスティガシオン、シモン・タンギー、オリヴィア・グランヴィルなどは、ランコントルのリピーターや、フランスでは知名度のあるアーティストで、個人的にはシモン・タンギーに非常に興味を持っている。また、日本からは南阿豆と三東瑠璃のふたりが選ばれているので注目したい。(詳細は3月中旬に発表予定)
http://www.rencontreschoregraphiques.com
|

