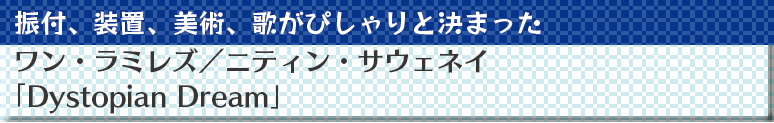

©Johan Persson
ドイツ生まれの韓国人ホンジ・ワンと、南仏生まれのセバスチャン・ラミレズのコンビ、カンパニー・ワン・ラミレズの人気が止まらない。ヒップホップベースのコンテンポラリーで、新作ごとに大きな反響を呼んでいる。
待ちに待った2017年の新作「Dystopian Dream」が、やっとパリに来た。これに関わる豪華なスタッフを見れば、このふたりが今や誰もが認めるダンス界の若手ホープということがわかる。プロダクションは、サドラーズ・ウエルズ劇場だし。世界で注目を集めているニティン・ソーニー(サドラーズ・ウエルズ劇場所属-ティスト)の音楽を、イギリスの若手人気歌手エヴァ・ストーンが澄み切った声で歌う。装置は、アクラム・カーンとシルビー・ギエムの「聖なる怪物たち」の舞台美術を手がけて、一躍著名になった美術家、針生康(はりうしずか)。そこにアクラム・カーンの作品を手がけたNick Hillel のビジュアルが映し出される。これらの優秀なアーティストが、「Dystopian Dream」という作品に集結した感じだった。
歌を口ずさみながら体を洗う女が見たものは、夢か現実か。永遠に続く白い階段、垂直に置かれた椅子に座る人、真っ黒な顔と頭の男、パンドラの箱を持つ女。シュールな世界がその家に潜む。不吉な気配を奏でるギターの音色はやがて、リズムのあるブルースとなる。テーブルでの3人のすれ違う会話、大きなムカデの登場、そこにいた人が消え、別のところから現れる。天に向かう階段がゆっくりと向きを変えた。永遠だったはずのものが、途中で途絶えている。それは、人生の終わりを暗示していたのだろうか。倒れた女の身体が、ゆっくりと天に昇る。
作品自体も面白いが、ホンジ・ワンの踊りがいい。広がりがあり柔軟な動きが印象に残った。(1月31日エスパス・ピエール・カルダン/THEATRE DE LA VILLE)
下記リンク先で動画をご覧いただけます。
https://www.youtube.com/watch?v=KmQ3hTgQDS4

©Johan Persson
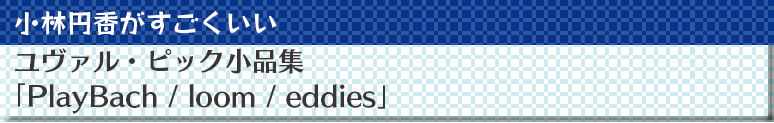
今から20年以上も前に、イスラエルから来たばかりのユヴァル・ピックは、パリ・ダンスコンクールで優勝した。渡仏して間もなかった私は、日本の現代舞踊界が良しとする美しく、軽やかに踊ることを求めていたので、どっしりと土臭い彼の踊りが評価されたことに違和感を覚えたのを、いまだに覚えている。そのユヴァルが、マギー・マランが建立した、リリュー・ラ・パップ国立振り付けセンターのディレクターとなり、そこで鍛えられた小林円香の踊りを見ていると、なぜ彼がコンクールで優勝したのかが納得できた。後から聞けば、当時のフランス人にもユヴァルの踊りは斬新なものだったらしいが、体の芯から使ったムーブメントには伸びがあり、身体の無限の可能性と存在感が見えるから、いつまで見ていても飽きない。人が作り出すムーブメントの面白さがここにある。
1月にシャイヨ国立ダンス劇場で発表された新作を逃してしまったが、過去の作品を見るのも悪くはない。ダンサー代われば作品も変わる。
「Play Bach」は、小林とふたりの男のトリオで、四角く囲まれた線の縁を、対面しながら移動しているうちに、枠の中に入った人との関わりを描く。このコンビネーションが変わっていて、相手の体に張り付くとか、持ち上げるとか、お互いに体重を掛け合う動きで、よくあるコンタクトとは質が違う。大きな男の体にぶら下がる小林の姿が愛らしく、かといってふたりに負けないパワーで押しまくり、そこにさらりと女性らしさを見せる。この兼ね合いが素敵だった。バッハの曲で繋げるからプレイ・バッハ、そして「遊び(プレイ)」という意味を重ねた、大人の真面目な遊びが面白い。

「Playbach」©AmandineQuillon
「Loom」は、女性ふたりの掛け合いが見もの、途切れるピアノ曲と、ふたりの呼吸する音が響く。ビデオで逆回しを見ているような、なぜこんなことができてしまうのだろうという動きがシュールで面白い。ここでも小林の切れとしなやかさが混合した踊りに、目が離せなかった。2014年の作品だけれど、ちっとも古くない。

「Loom」©Amandine Quillon
「Eddies」は、本日の出演者総出(と言っても4人なのだが)の作品で、ものを叩くような音の中での踊りは、前の2作よりダンスらしい振付が入っていて新鮮だった。髭を生やしたアドリアン・マルタンの踊りに、昔のユヴァルの姿が重なり、入団してまだ2年という彼に、さらなる期待をしたいと密かに思った。
3作品とも、そこに感情とか物語はないけれど、動きの連続の中にさらりとお互いの関係を見せる。その感情があるようでない無言の会話と、身体の可能性が感じられるムーブメントとのコンビネーションが、ユヴァル独特の作風で、私は気に入っている。
3月7日から13日まで、大阪阪急うめだ本店9階祝祭広場で開催されるフランスフェアで「Loom」を上演するそうなので、ぜひ! 上演日程などは、アンスティチュ・フランセ関西まで問い合わせてください(06-6358-7391、http://www.institutfrancais.jp/kansai/)。入場無料というのが嬉しい!
以下が3本まとめたビデオです。
https://vimeo.com/192618296

「eddies」©Mélanie Scherer
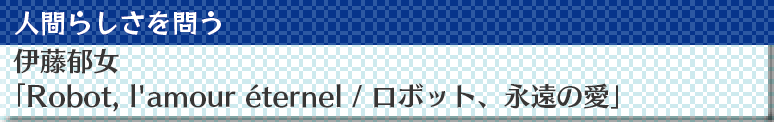
フランスで、いやおそらく世界中で人気が高まる伊藤郁女。新作「ロボット、永遠の愛」は、ロボット化が進む現代に於ける人間性、そして生と死をテーマにしている。
ゆったりとしたピアノ曲が流れる中、四角い台の上を覆う薄い白い布。そこに人らしきものが横たわり、ところどころにセルロイドの人体の破片が散らばっている。ゆっくりと動いていた人影は、いつの間にか消えた。そして、白い布が四角い穴の中へ静かに引き込まれていった。別の穴から足が出ていて、ゆっくりと現れた伊藤は、顔に面の破片を着け、人形振りのような動きをしている。アンドロイド伊藤だ。セルロイドの破片は、ロボットという殻を破り捨てたのか、あるいは偶然に割れてそこから本来の姿が現れたということなのだろうか。破片となった身体の一部を着けてみるけれど、昔には戻れない。人間? それともロボット? BGMは2年前の日記。X月X日オーストリア、X時X分空港に着いた。ホテルに着いた。疲れた。X月X日、スイス、ドバイ、 暑い…。自己を見失うほど忙しいスケジュールをこなしていた時期だろう。それまでの人形振りのようなムーブメントが、少し人間味を帯びた頃、ねじれた布がゆっくりと股の間を通った。へその緒。新たな命をこの世に送り出したことで、何かが変わる。アンドロイドから人間へ。命があれば、いずれは死を迎える。避けられない事実であれば、それを喜んで受け入れようということなのだろう。人間となった伊藤は、Vサインをしながら穴の中に消えていった。
伊藤の父とのデュエット「私は言葉を信じないから踊る」で、伊藤の飾らないプライベートが見えたのが印象に残っているが、今回は、さらにそこから一歩踏み出して、世界に出た伊藤の歩みを振り返っている。前作に比べてダンスの要素が多かったのは、伊藤の踊りが見たいファンにとっては嬉しいことだったが、サクッと作品には入れないものを感じた。それは、言葉が多かったことと、その内容が想像力を阻んだからだろう。また、アンドロイドから人間へ移行し、それが生と死につながる流れで、伊藤が突然観客と対話した時に、それまでの余韻がプツリと切れてしまった。伊藤とのアドリブ会話は面白いけれど、この作品に必要だったのだろうか。これがひどく残念に思えた。(1月27日MACクレテイユ)
下記リンク先で動画をご覧いただけます。
https://www.youtube.com/watch?v=TQx4za6z7XQ

©Dylan Piaser
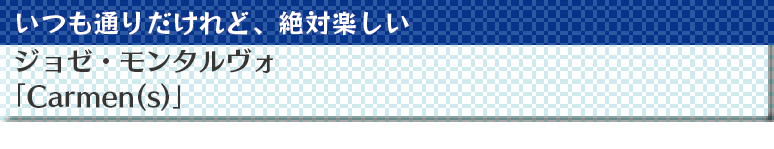
バレエにコンテ、ヒップホップに民俗舞踊をコラボして、さらに映像と一緒に踊ってしまう作品で超人気のあるジョゼ・モンタルヴォ。新作「カルメン」は、期待を裏切らない楽しさいっぱいの作品だった。「いつもと同じ」だし、フラメンコがテーマの「Y Olé !」と韓国国立舞踊団とのコラボ「Shigané naï」を合わせたような感じだったけれど、楽しいことに間違いはない。
女性は全員が赤のワンピース。つまり、全員がカルメン。だからタイトルも()付きで複数形。それに対抗する7人の男たち。ヒップホップのテクで個性豊かな女性陣に食いかかるけれど、どこかでうまく巻かれてしまう。男の挑発にフラメンコで打ちのめし、バレエやコンテンポラリーダンスで応える女性たち。そんな中でちょっと異質な韓国舞踊。ひとりゆったりと優雅に宮廷舞踊をしている。このギャップが面白い。男どもの攻勢を一蹴するかのように、オレ! の叫び声が響き、踊りと歌の饗宴が続く。そこに牛! もちろん映像の中だけれど、カルメンだから牛の出番があるわけで、この牛たちに追いかけられ、追い越し、飛び越すダンサーたちの元気なこと。そして韓国の軽快な太鼓のリズムに、思わずリズムを刻んでしまう。韓国もアフリカも。軽快な太鼓のリズムに違いはない。
ダンサーひとりひとりがカルメンへの想いを語る。カルメンのように自由奔放に生きられたらどんなに素敵なことだろうか。そんなカルメンに誰もが憧れる。それぞれのカルメンだし、自分だってカルメンになれるはず。またもや元気をもらった。欲を言えば、男性ダンサー全員がホップホップなのではなくて、今タンポラリーやフラメンコ、バレエダンサーがいても良かったのではないかしら。(1月27日MACクレテイユ)

©Patrick Berger


©Mats Backer
ミッキーマウスやピーターパン、スーパーマンにバットマン、誰もが知っているキャラクター。それは映画や写真で世界中に広がった、それを撮ったのがコダックカメラ。そこでカメラ目線で作品を作ったということらしい。
小島章司とのデュエット「Simulacrum/シュミレイクラム」もそうだったように、作風は映画的。演劇からダンスに入った人だから、バリバリのダンス作品とは違う視点で作っている。ラッキーストライクの広告がついた公衆電話の横で、電話が鳴るのを待つ男。ふかすタバコはラッキーストライク? 登場したミッキーマウスは、語り部にもなるし、主人に連れられた犬にもなる。
「家に帰らなくちゃ」「あら、お帰りなさい」「僕は誰?」
記憶が飛ぶ、時間が飛ぶ、いつものことが、当たり前の日常がずれていく。「ようこそ、本当の世界へ!」何がフィクションで、何がノンフィクション?
場面はくるくると変わる、道、墓場、家の中。1本の木や、公衆電話が上下しての場面転換は、瞬時に状況が切り替わり、映画の場面転換のようで違和感がない。そしてたった1回だけ、ラスト近くに暗転の場面転換。これは効果的だった。それまでが夢の中の出来事のようにいつの間にか環境が変わるのに、ここではくっきりと場面が変わったことを印象付ける。そして、何事もなかったように現実に戻り、いつもの日常が始まる。フラッシュバックを見ているように、アニメや映画の登場人物や、ハリウッドやミュージカルを連想させるようなシーンが連なる。それはそれで面白いのだけれど、何しろ言葉が多いし、70年代のアメリカ商業芸術に精通していなければ、心底楽しめない。面白いけれど、完全に理解できないというジレンマに陥って、消化不良状態。
出演したスウェーデンのヨーテボリ・オペラダンスカンパニーのレベルは高く、気持ち良いほどにサクッと難しい振りをこなしている。踊って良し、演じて良し、喋って良しで、あらゆる要素が詰まった作品をこなしていたのは見事だった。日本人では、山田アリカが出演していた。日本語吹き替え版でもう一度見てみたい。(1月25日シャイヨ国立ダンス劇場)

©Mats Backer

50回目を迎えたアップデイトダンスは、「ピグマリオン-人形愛」。「ピグマリオン」といえば、ギリシャ神話やジョージ・バーナード・ショーの戯曲(「マイフェア・レディ」の原作ともいわれる)で有名だが、勅使川原は、人形と人間の間に埋もれる奇異な感情を独自の世界で表した。
薄暗い舞台の中央に人が座っているのがうっすらと見える。椅子から垂れたスカートが、女性だということを暗示している。全く動く気配のない女性の後ろに、静かに現れた影。人形振りのような動きをしながら、ゆっくりと女性に近づいていく。暗い空間にうっすらと浮かぶ顔と、小刻みに動く手のムーブメント、そして隙間風とも獣の声とも取れる音が、不吉な予感をもたらしている。人形を愛するあまりに、自身が人形になったような男は、ゆっくりと人形に触れた。魔法をかけられたように、人形はゆっくりと動き出し、やがて激しく踊り出した。男も高まる感情の中で激しく動き、それが頂点に達した時に女を抱きしめた。しかし、それはこの夢の終わりだった。高揚した音楽が動物の叫び声と重なった時、女は崩れ落ちた。愛するあまりの出来事だったのか、あるいは、人形にはもともと死など存在せず、これはただの幻想だったのだろうか。
文学作品などを基に、独自の世界を作る勅使川原。今回も、緻密な構成と、シンプルに見えて非常に計算された照明と、音の使い方に「完璧」としかいいようがなかった。そして、勅使川原の世界を深める佐東がまたいい。前半はほとんど動かず、疲れ知らずに踊る佐東の姿を想像していただけに、意外な感じだったが、ゆっくりと動き出した後に、弾けるように踊り出した。ただ、いつもと違って、あくまでも人形というスタンスの元に踊っている。自分の意思のようで、どこか操られた動きは、作品をとことん理解しているから生まれたのだろう。ここ数年の佐東の踊りは素晴らしく、さらなる深みを増している。
この後ふたりはフランスに渡り、「トリスタンとイゾルデ」を踊るだけでなく、ロレーヌ・バレエ団に振付をするという。勅使川原の湧き出る創作力は尽きることを知らないようだ。(1月7日カラス・アパラタス)

|

